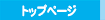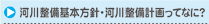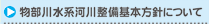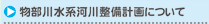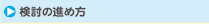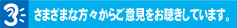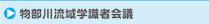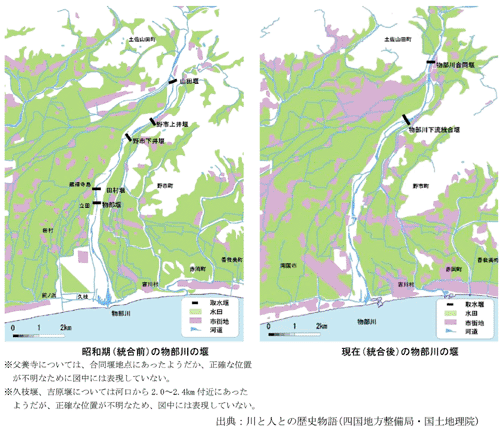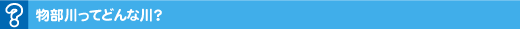
利水編 〜貴重な水を供給する川〜
利水事業
物部川下流部の河道は、かつては洪水のたびに頻繁に流路が変化し、自然に近い
状態で地形的に低い部分を流れていたため、平常時の水位は周辺の地盤高より低く、
取水堰は存在していたものの、かんがい等の水利用には限界があったと推定されます。
このため、川沿いの平地は、江戸時代初期までは荒れ地が多く、わずかに畑地がみられる程度でした。しかし、寛文(かんぶん)4年(1664年)に土佐藩家老職の野中兼山が山田堰を建設し、香長平野にかんがい用水路網を整備するとともに、治水対策を行い、
ほぼ現在に近い位置へ河道を固定化したことなどにより、以降、水田の開発が進み、
物部川の水と温暖な気候、肥沃な土壌を背景に二期作が盛んに行われる穀倉地帯へ
と変化しました。
それでも、物部川流域では、降雨が6月から9月の梅雨期と台風期に集中して一時
に降るため、晴天が続けば河川の流水が急激に減少し、農業用水に不足をきたすことが多かったのです。このため、大正時代より吉野川水系からの分水やダム建設等の対策案が提起されていました。昭和32年3月には物部川総合開発事業の一環として永瀬ダムが竣工したことから安定的な取水が可能となり、二期作を前提とした早期栽培をめぐる水利紛争はなくなりました。その後、物部川下流部に存在していた山田堰を含む8堰は、昭和41年完成の統合堰
および昭和48年完成の合同堰の2つの取水堰に統合されました。これらの利水事業により、現在も物部川の水は香長平野の重要な水源となっています。
物部川の8堰の統廃合は、昭和34年の南国市誕生の際に、下流側の6堰(野市上、野市下、田村、物部、久枝、吉原)からの要望により計画されたものです。当初は、8堰全てを1つの堰に統廃合する計画でしたが、上流の山田堰では永瀬ダム完成により取水が極めて順調であったため、堰着工の見通しがつきませんでした。
その後、昭和38 年台風9 号の被害を契機として、下流6 堰のみでの統廃合が図られ、昭和41 年に統合堰が完成しました。
また、上流2 堰(山田、父養寺)では、舟入川上流部の水路コンクリート化に伴い統廃合が図られ、昭和48 年に合同堰が完成しました。
野中兼山の遺構である山田堰については、一部を史跡として残した河川公園に再生し、住民に親しまれる施設として生かしました。
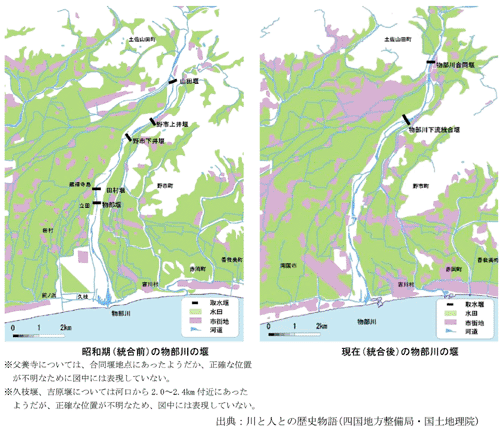
上の図をクリックすると大きな図を見ることができます。
永瀬ダム
永瀬ダムは、物部川総合開発事業の一環として、洪水調節とかんがいと発電を目的に、昭和32 年3 月に完成しました。
かんがい用水は、香長平野の3,650ha にかんがい補給しています。
ダム諸元
| 目的 |
洪水調節、発電、不特定 |
 |
| ダム竣工 |
昭和32年 |
| 形式 |
重力式コンクリートダム |
| 堤高 |
87.0メートル |
| 集水面積 |
295.2平方キロメートル |
| 総貯水容量 |
4,909 万立法メートル |
| 有効貯水容量 |
治水:2,232 万立法メートル ※2
利水:2,355 万立法メートル ※2 |
| 計画堆砂量 |
1,350 万立法メートル ※1 |
762 万立法メートル ※3 |
| 発電所名 |
永瀬PS |
| ダム事業者 |
建設省中国・四国地方建設局 |
| ダム管理者 |
高知県 |
※1 当初計画
※2 昭和38 年の測量結果に基づき現在の操作規則に見直した値
※3 昭和38 年の測量結果に基づき算出した計画堆砂容量内の空容量
|