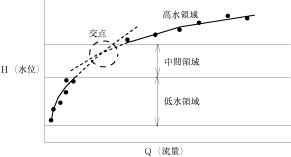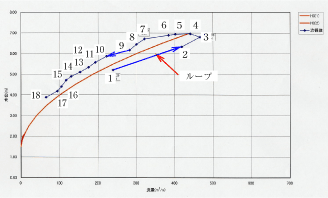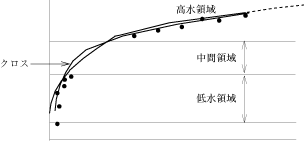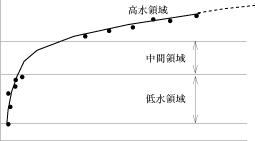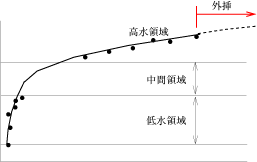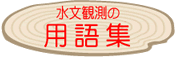 |
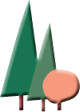 |
|
目 次 |
|
| 1.用語集の目的 2.水文観測全般(1) 2.水文観測全般(2) 3.雨量観測 4.水位観測 5.高水流量観測(1) |
5.高水流量観測(2) 6.低水流量観測 7.H-Q曲線 8.資料整理 9.痕跡調査 10.参考文献 |
|
五十音順 |
|
7.H-Q曲線 ←前章 次章→7.1.H-Q曲線一般に、流量は連続的に観測することができないが、水位は連続的に観測できる。観測地点の水位(H)と流量(Q)の関係を求め、連続的に観測できる水位データにより、観測した水位に対応する流量を算出することができる。H-Q曲線とは、水位と流量の関係をグラフ化したものであり、一般に、二次曲線で作成される場合が多い。ある期間において、水位(H)と流量(Q)の関係が1対1で対応していることが前提である。H-Q曲線は、水文データ整理,流出解析,危機管理などの資料として活用される。
7.2.ループ洪水時、河床勾配の緩やかな河川では、水位上昇期と下降期の同じ水位において流量を比較すると、水面勾配の影響を受けて、洪水上昇期の流量の方が多い現象が見られることがある。このような洪水データをH-Q図に描くと反時計周りの楕円状の軌跡となるため、これをループと呼んでいる。一般の河川においても、ループ(または逆ループ)を描く観測所もあり、今後の知見が待たれる。
7.3.クロスクロスとは、H-Q曲線作成において、中間領域付近でH-Q曲線が交差することをいう。河床変動が頻繁に起こる観測所では、低水領域でのクロス発生はやむを得ない。高水領域でのクロスはあり得ない。 「クロス」は、四国水文観測検討会で慣例的に用いられた言葉である。
7.4.中間領域流量観測は、低水流量観測と高水流量観測に分かれて観測を行っている。中間領域とは、低水流量観測可能上限水位と高水流量観測可能下限水位との間に生じる観測不可能領域のことである。観測に際しては、H-Q曲線の精度向上のために中間領域の観測を極力行う(中間領域を狭める)ことが、努力目標とされている(ただし、観測精度が不良であると判断できる場合は観測しなくて良い)。「中間領域観測」は、四国水文観測検討会で慣例的に用いられた言葉である。
7.5.外挿外挿とは、水位流量曲線(H-Q曲線)を作成する上で、H-Q曲線作成に使用した観測データの上限,下限値を越えて、上方または下方に曲線を延伸することをいう。精度が悪く、利用には注意が必要である。
|
7.6.精度管理図流量観測において、観測結果が妥当であるか否かを判断する資料として、昨年作成したH-Q図,H-√Q図,H-B図,H-V図,H-A図などに本年度の観測値をプロットした図を作成する。精度管理図とは、これらの図のことをいう。特にH-Q図,H-√Q図は重要である。 |