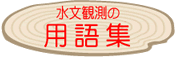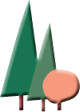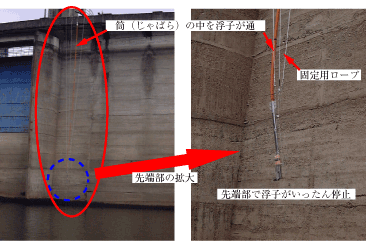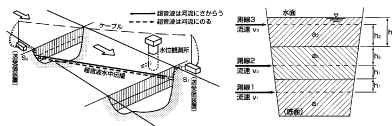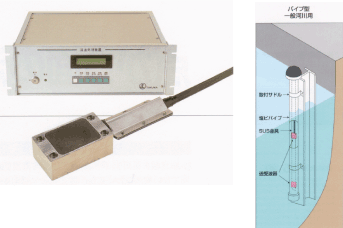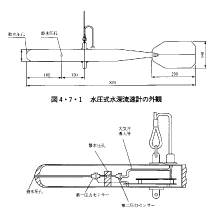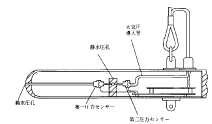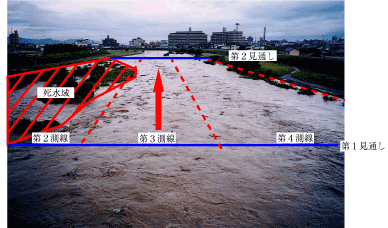|
高水流量観測における浮子法では、河川の横断方向において測線分割を行い、その全ての測線について流速を測定すれば1観測が終了する。観測サイクルタイムとは、これに要する時間のことであり、必然的に観測時間ピッチは、観測サイクルタイムより大きくなければならない。
浮子投下機とは、橋梁がない観測所において、浮子を投下するために用いられるものである。川の両岸に柱などを設け、それに張られたワイヤーに沿って動く無人のロープウェーのようなものが、測線分割に応じた横断距離においてフックをはずすことにより、浮子を投下できるようにしている装置のことである。
浮子を投下する位置が水面から高い観測所では、浮子を投下したとき、浮子が水面から深く沈み、第一見通しを通過する時点で浮き上がってこない場合や浮子の流れが安定しない場合がある。橋梁浮子投下装置とは、このような現象を緩和することを目的として水面近くで浮子を投下できる装置のことである。「橋梁浮子投下装置」は、四国水文観測検討会独自の呼称であり、一般には用いられていない。
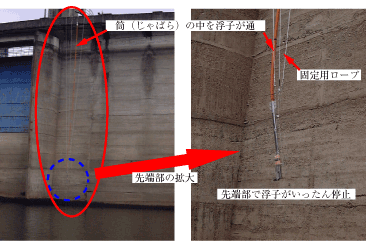 |
| 写真:橋梁浮子投下装置の例1 |
 |
| 写真:橋梁浮子投下装置の例2 |
光波測距儀は、光を発射し、目的点においた反射鏡からの反射光の位相差により、距離の測定を行うための測量機器である。光源には、発光ダイオードやヘリウムネオンレーザーなどが用いられる。ヘリウムネオンレーザーを用いたものでは、60km程度まで測定可能なものもある。
光波測距儀による流量観測とは、反射鏡の代わりに反射シートを貼った浮子を河川に流し、光波測距儀により平面座標と移動距離と時間から流速を計測する観測方法である。通常の浮子観測に比べて、3次元データを得ることができる。
 |
| 写真:光波測距儀 |
| 出典:株式会社 SOKKIAレクノス測量用品カタログ |
流速プロファイラー(ADCP:Acoustic Doppler Current Profiler)とは、水中に超音波を発信して、ドップラー変調を受けた反射音の周波数を解析することにより、河道断面内の3次元の流速分布を測定する装置である。固定式と曳航式の観測方式がある。機器特性として、水面付近及び河床付近の流速は観測不能である。
 |
| 写真:ADCP本体 |
| 出典:株式会社 エス・イー・エイ ADCPカタログ |
電波流速計とは、流水の水面に電波を照射し、ドップラー効果を利用して表面流速を求める装置である。橋梁などに添架し、河川の表面流速を連続して観測できる観測装置であり、流水に直に接しない非接触型となっている。流速が小さく鏡のような水面では測定できない。流量観測等によりあらかじめ求めておく鉛直方向平均流速の換算係数の精度が流量に影響する。風の影響を受けるため、風向風速計の併設が必要である。また、取扱者は電波法に基づく資格を有する必要がある。
 |
| 図:電波流速計 |
超音波流速計とは、上流から下流へ超音波が伝播するのに要する時間と、反対に下流から上流へ伝播するのに要する時間の差は、超音波伝播線上の平均流速に比例する原理を応用した観測装置である。
1対の超音波送受波器をそれぞれ左右岸の水中に斜めに設置する。送受波器は、水深に応じて鉛直方向に複数個(左右岸で1対)設置し、各層の平均流速を積分すれば流量が求められる。
超音波流速計は、浮遊物,水温による影響,複断面では不適など欠点もあるが、24時間無人で連続観測が可能などの利点もある。
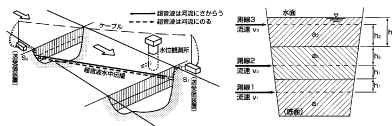 |
| 図:超音波流速計のモデル図 |
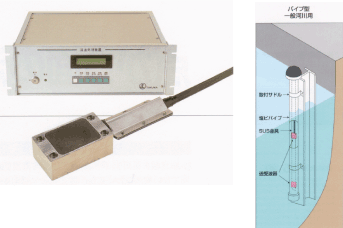 |
| 図:超音波流速計写真及び設置イメージ |
水圧式水深流速計とは、ピトー管の原理を応用して、河川の水深と流速を同時に測定する装置である。従来の流速計では測定が困難である洪水時の河道断面内の流速の鉛直分布を直接測定することができる。観測に際しては、流下物による破損の恐れがある。また、流速の大きな河川では、おもりを重くしたり、機器の保持方法にも工夫が必要である。
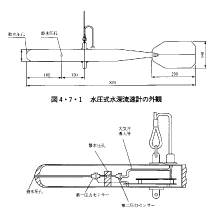 |
| 図:水圧式水深流速計モデル図 |
ピトー管とは、ヘンリー・ピトーが開発した後部が閉じた管で、上流端に小さな開口をもった管によって全水圧(静水圧と流速に対する動水圧の和の圧力)を測定する装置である。ピトー管により全水圧を測定し、静水圧を除いた圧力をもとに流速を算定することができる。
全水圧=動水圧+静水圧
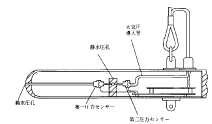 |
| 図:ピトー管の原理モデル図 |
静水圧とは、静止している水中で作用している水圧のことである。
①静水圧の大きさは水深に比例する。
②一定に作用する静水圧はどの方向からも同じ大きさで働く。
③面に作用する静水圧は面に垂直に作用する。 |
|