■ヨシ群落
 |
 ■識別ポイント・構成種 河口域のとろ場や湾入部、池などの止水から緩やかな流れのある水際にヨシが優占していることで識別できる。ヨシはイネ科の多年生草本で高さは2m 以上に達する。外見はツルヨシとそっくりであるが、地上茎(地上走出枝:ランナー)を出さないこと、流水のある場所や礫地には成育しないことから識別できる。 ■構成種 群落高は2m を越えることもあり、階層は2 層に分かれる。第一層はヨシが圧倒的に優占し、下層にミゾソバ、セリ、スギナ、ヒメジソなどがわずかに成育する。また、河口域ではシオクグ、ハマサジなどの塩沼地の植物とも混生する。それらの群落については区分する必要があるかもしれないが、今回はヨシの優占群落はすべてヨシ群落として区分してある。構成種数はおよそ7 、8 種である。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 過湿な泥〜砂質の立地である。また潮にも耐性があり河口域の汽水域にも成立する。ヨシの持つ生態的機能は多様であり、水中ではカニや小魚のすみかやトンボ類産卵などに利用され、地上部ではオオヨシキリ、セッカなどの鳥類の生息場や隠れ場など多くの生物に利用されている。また、水中の茎に付着したコケ類により水質を浄化する働きもあり、ヨシを用いた浄化システムについては各地で試験が行われている。 ■隣接する群落 河口域では、シオクグ群落、ハマサジ群落、淡水域では陸側にオギ群落、ヤナギ林などにつながる。 ■四国での分布 河口、下流部を中心に全ての河川で確認されている。肱川は下流部が山付きであること、中上流域でも止水環境が少ないことから、分布が少ないものと考えられる。 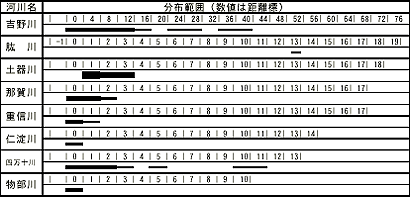 ■保全上の留意点 大面積で成立しているものは、上述したとおり非常に重要な環境機能を有しているため、保全しておく必要がある。ヨシ群落が全て重要な群落ではなく、群落の規模、周辺環境との兼ね合いなどから重要性、保全の必要性を検討するべきである。ヨシは比較的攪乱に強く、成育も旺盛であるが、保全においては立地の水湿条件を変えないように注意する必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 ヨシの植栽については、琵琶湖湖岸において近畿地方整備局琵琶湖工事事務所や滋賀県などにより、霞ヶ浦湖岸におて茨城県霞ヶ浦対策課関東地方整備局霞ヶ浦工事事務所などにより研究が進められている。ヨシの増殖、移植法は地下茎をつけたままの株移植法、地下茎の移植法、地上茎を挿し木で増やす方法、播種による増殖法などが検討されている。もっとも活着率が高く、実用的なのは地下茎をつけたままで株を移植する方法である。また、(財)琵琶湖・淀川水質保全機構(電話(06)‐ 6202‐ 1267 )から「琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センタ−年報第1 号、第2 号」が発行されており、ヨシの移植試験結果が公開されている。 ■植物社会学上の位置づけ ヨシの優占群落は群集レベルでの位置づけはされていないが、上級単位はヨシ群団、ヨシオーダー、ヨシクラスに所属する。 |
|
|