| ■ガマ群落 類似群落:ヒメガマ群落・マコモ群落
 |
 ■識別ポイント 湾入部などの水際にガマ、ヒメガマ、マコモが優占していることで識別できる。ガマ、ヒメガマはガマ科の多年草で地下茎を伸ばして繁殖する。ヒメガマはガマよりも葉が細く、雄花と雌花の花序にすき間があく(右図)。マコモはイネ科の多年草でガマやヒメガマと同様な立地に成育し、時に混生する。 ■構成種 いずれも草丈は1m 〜2m に達し、第一層はガマ、ヒメガマ、マコモが優占する。水深が深いと一種のみの純群落となり、浅いと下層にミゾソバ、キシュウスズメノヒエなどが成育する。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 過湿な泥質地に成立する。一般的には常に滞水した池状の立地に成育する。上記の肱川のような河口域の干潟に成育するのは珍しいと思われる。湛水域では、トンボやカエル類や水鳥などの生息、かくれ場などに利用される。 ■隣接する群落 ヤナギ林、オギ群落などに隣接する。 ■四国での分布 面積は小さいが下記の6 河川で成立している。土器川の潮止堰上流側左岸に、まとまった面積でヒメガマ群落が発達している。 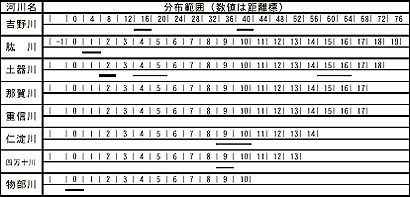 ■保全上の留意点 水際から陸域へのエコトーンを形成し、環境の多様性を高める上でも重要な群落である。ヨシ群落同様、発達した群落は保全しておく必要がある。各植物は比較的攪乱に強く、成育も旺盛であが、保全においては立地の水湿条件を変えないように注意する必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 根茎を掘りとって、ブロック状に植えると活着する(桜井、1989 )。だだし、常に湛水していることと植栽基盤が波などに流されないよう土留めの工夫が必要である。 ■植物社会学上の位置づけ マコモを含む群集はマコモ−ウキヤガラ群集があり、ヨシ群団、ヨシオーダー、ヨシクラスに所属する。ガマ群落、ヒメガマ群落に対応する群集はないが、マコモ群落同様、ヨシ群団、ヨシオーダー、ヨシクラスに所属するものと考えられる。 桜井善雄.1989 .沿岸帯水域の緑化.「最先端の緑化技術亀山章他編」.197‐ 212pp .ソフトサイエンス社.東京 |
|
|