| ■ヒシ群落 【在来植物群落】 類似群落: 【在来植物群落】 コオニビシ群落 コウキクサ群落 【外来植物群落】 ホテイアオイ群落
|
 ■識別ポイント・構成種 河川の湾入部または池状の止水域に各植物が群生していることで識別できる。ヒシ、コオニビシはヒシ科の一年草、南米原産のホテイアオイはミズアオイ科の多年草であり、しばしば止水域の水面に大群落を形成する。コウキクサは3 〜5mm のごく小さなウキクサ科の一生草であり、水田や溝などに群生する。それぞれ、ほとんど1 種の純群落を形成する。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 ヒシ、コオニビシ、ホテイアオイは富栄養な止水域に大群落を作る。時に水面を覆い尽くし、冬には枯れるので、水質の悪化などがしばしば問題となる。ホテイアオイは、浮遊して着岸した場所から根を下ろし、株が分かれて旺盛に増殖する。水面を適度に被っているときは、トンボなどの水生生物の生息、産卵場として利用されるが、水面を完全に覆い尽くすと、水が腐敗することもある。 ■四国での分布 コウキクサ群落は重信川のごく小さな水たまりだけで確認したものである。ヒシ群落は四万十川の支川の中筋川および肱川の10km 左岸にある竜王池で確認している。コオニビシ群落は吉野川に点在している。一方、ホテイアオイは吉野川で広く確認されており、漂流したものが止水や緩やかな流れの水域で群落を形成しているものと考えられる。しかし、これらの群落は河川の流水環境とはあまり結びついておらず、河川敷の狭い河川や流れの速い河川では、群落としての定着は困難であろう。 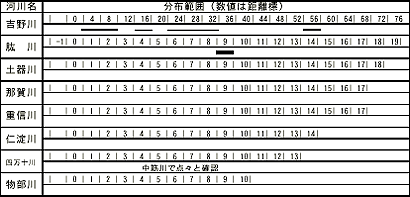 ■保全上の留意点 群落としての貴重性は高くなく、特に保全する必要はない。逆に、湾入部や池などの止水域で密生する場合は、水質や水中の生物へ悪影響を及ぼすことも心配されるため、冬季の枯れた個体などを除去する管理が必要であろう。 中国地方整備局岡山河川工事事務所が管轄する百間川(岡山県)では、かつてホテイアオイが繁茂し、その除去方法などについて検討されている。 ■植物社会学上の位置づけ ヒシ群落、コオニビシ群落、ホテイアオイ群落の上級単位は、ヒツジグサ群団、ヒツジグサオーダー、ヒルムシロクラスであると考えられる。 コウキクサ群落の上級単位は、アオウキクサ群団、コウキクサオーダー、コウキクサクラスに所属する。 |
|
|