| ■エビモ群落 【在来植物群落】 類似群落: 【在来植物群落】 ササバモ群落 セキショウモ群落 クロモ群落 【外来植物群落】 オオカナダモ群落 コカナダモ群落 オオフサモ群落
|
 ■識別ポイント・構成種 河川の流水・止水域中で各植物が繁茂していることにより識別できる。オオカナダモ、コカナダモはしばしば単独で大群落を作る。共存する種はほとんどなく、それぞれが単独で成育する。オオフサモは葉を水面に出し抽水性となる。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 流水、止水域などに成立する。いずれの植物も定着すると比較的まとまった面積で群落を形成する。魚介類などにとって、重要な生息環境を提供している。各外来植物群落は河川水や河床材料の富栄養化にともない、各地で拡大しつつある。 ■四国での分布 在来植物群落であるエビモ群落は吉野川、土器川、ササバモ群落は吉野川、四万十川、セキショウモ群落は四万十川と肱川にそれぞれ分布しているが、植生図に表現できないほど小さい(そのため、次ページの分布範囲には表現できていない群落もある)。四万十川では在来各種の沈水植物群落が確認されており、流水域の環境の良好さを物語っている。一方、オオカナダモ、オオフサモ群落は吉野川、肱川、重信川、仁淀川で確認されており、面積も広い。 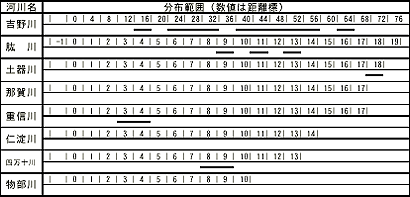 ■保全上の留意点 エビモ群落、ササバモ群落、セキショウモ群落、クロモ群落は各河川ともに少なく、是非とも残しておきたい植物群落である。それ以外の外来植物群落は、大繁茂して在来の群落を駆逐するおそれもあり、繁茂しすぎる場合は除去するなどの管理が必要であろう。 ■保全・創出に関する事柄 各在来種の流水中の群落の保全に関しては、日本各地で課題となっている。しかし、具体的な保全法、創出に向けた事例はほとんどない。止水域の場合は、根茎の移植などで再生の可能性はあるが、流水中では非常に困難になることが予測される。 ■植物社会学上の位置づけ 各沈水植物群落の上級単位は、バイカモ群団、ヒルムシロオーダー、ヒルムシロクラスである。 |
|
|