| ■ハマゴウーチガヤ群落 参考群落:テリハノイバラ群落
 |
 ■識別ポイント・構成種 発達した海浜砂丘の後方で、ハマゴウが優占しチガヤが混生することにより識別できる。ハマゴウはクマツヅラ科の矮生低木で匍匐(ほふく)しながら分布を広げる。高さは0.5m 程度である。構成種はハマヒルガオ、ネズミムギなど6 〜9 種である。なお、テリハノイバラ群落は海岸などに成立する群落で、重信川河口のみで確認されている。 ■成育立地の環境特性 河口域の発達した海浜、砂丘の後方の乾燥した砂浜に成立する。また、海岸付近の法面に二次的に成立することもある(写真右:那賀川)。 ■生態的機能 前述のコウボウムギ群落やハマエンドウ群落の後背に成立する帯状の分布構造を持ち、海浜植生や砂丘を安定させている。 ■隣接する群落 水域の前面に、コウボウムギ群落やハマエンドウ群落などに接し、陸域では高水敷や造成地の植生につながる。 ■四国での分布 発達した群落は那賀川の海浜で確認されている。重信川、四万十川の群落は面積も狭く状態はよくない。また、今回の踏査で物部川の河口にヨシ群落に埋もれるように成立している群落を確認した。 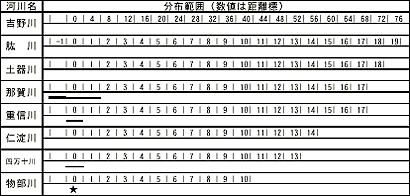 ■保全上の留意点 コウボウムギ群落、ハマエンドウ群落同様、海浜に成立する自然植生として重要である。那賀川では水際からコウボウムギ群落、ハマエンドウ群落、本群落と帯状の分布構造ですみ分けており、海浜の自然な形態として重要である。しかしながら、他河川では本群落の発達が悪い。肱川の河口の浜など潜在的には成立できる立地もあり、復元が望まれる群落である。 ■保全・創出に関する事柄 創出に関する事例はない。ハマゴウは園芸資材として流通しており、挿し木などによる増殖は比較的容易である。ただし、各河川で復元を考えるときは、近年問題となっている「遺伝子の攪乱」防止の観点から、その河川に成育しているハマゴウを増殖し、復元を図るべきである。 ■植物社会学上の位置づけ ハマゴウ−チガヤ群集、ハマゴウ−ケカモノハシ群団、ハマゴウオーダー、ハマゴウクラス |
|
|