| ■コウボウムギ群落 類似群落:ハマエンドウ群落
 |
 ■識別ポイント 発達した海浜砂丘上に、コウボウムギまたはケカモノハシが優占することによりコウボウムギ群落に、ハマエンドウの優占およびギョウギシバの成育によりハマエンドウ群落に識別できる。 発達した海浜であれば、微地形により両者の群落が明瞭に区分されるが、河口域の狭い海浜では両群落が混在するようになる。 ■構成種 両群落ともに共通する種としてハマヒルガオ、ケカモノハシ、コマツヨイグサなどがある。構成種数は、2 〜9 種程度である。 ■成育立地の環境特性 河口域の発達した海浜、砂丘に発達する。 ■生態的機能 各植物は風による砂の移動、埋没という厳しい環境に耐えながら成育している。厳しい自然条件には耐性があるものの、車の過度な乗り入れによる踏圧や改変には非常に弱い。また、吉野川河口の海浜には希少な昆虫であるルイスハンミョウが生息する。 ■隣接する群落 水際は砂浜であり、後背にはハマゴウ−チガヤ群落が接する。 ■四国での分布 吉野川、那賀川の海浜、砂丘が発達した河口域にのみ確認されている。肱川の河口砂丘にはハマヒルガオなどの海浜性の植物が成育しているが、人や車の進入により攪乱されまばらに成育するのみとなり、群落としてのまとまりはなくなっている。 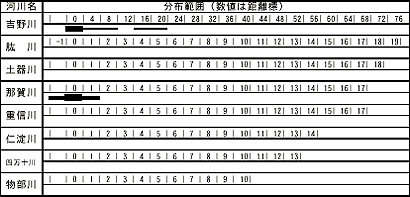 ■保全上の留意点 海浜に成立する自然植生として重要である。上述したように海浜という不安定な立地に成立するものの、人為的影響には弱く、直接的な改変、人や車の過度な乗り入れには十分注意を払う必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 徳島県土木部空港地域整備課により、コウボウムギやケカモノハシなどの保全や移植に関する試験・調査が現在進められている。 ■植物社会学上の位置づけ コウボウムギ−ハマグルマ群集、ケカモノハシ−ウンラン群集などが報告されているが、今回の調査資料は少なく、群集の同定は保留にしておく。なお、上級単位はコウボウムギ群団、コウボウムギオーダー、ハマボウフウクラスである。 |
|
|