■ヨモギーメドハギ群落
|
 ■識別ポイント 水際から一段ほど高くなった乾燥した丸石河原には、カワラヨモギ、メドハギ、ヨモギ、マルバヤズソウなどが混在し、まばら(写真左・右下)または密に(写真右上)群落を形成している。優占種は顕著ではなく、後に述べる河原特有の植物を含むことになどより特徴づけられる。河床勾配がきつく、礫原の発達した四国の河川を特徴づける植生であり、多くの河川特有の植物を含むことから重要な群落と考えられる。 ■構成種 群落高は1.5m 程度であり、上記の種やカワマツバ、カワラナデシコが高い頻度で出現するほか、カワラサイコ、カワラハハコ、ハマウツボ、イヌハギなど「カワラ(河原)」と名前の付く植物などが多く含まれる。こられの内、イヌハギは環境省により絶滅危惧˘種に指定されているほか、カワラハハコ、カワラサイコ、ハマウツボは近年、減少が著しい種である。構成種数は10 〜28 種である。  ■成育立地の環境特性 増水時には冠水するが常時は非常に乾燥している河原であり、植物にとって非常に過酷な環境である。また、1 年または数年に1 度は冠水し、地表の有機物や土壌などが洗い流される。 しかしながら、近年では水質の悪化、ダムなどによる冠水頻度の低下などから、立地の富栄養化が進み、セイタカアワダチソウやカナムグラ、クズなどのツル植物の侵入が多くなり、良好な組成を持つ群落が減少している。ハマウツボは物部川河口域には多いものの、土器川などではほとんど絶滅し、カワラハハコも各地で激減している。 ■生態的機能 河原という過酷な環境に適した在来植物の群落であり、独自の生態系を有している。 バッタ類やチョウ類などの昆虫やヒバリなどの鳥類にとって、重要な生息環境となっている。 ■隣接する群落 水際にツルヨシ群落、ヤナギタデ−オオイヌタデ群落、陸側の安定した立地にはノイバラ群落などにつながる。 ■四国での分布 吉野川では、後述のヨモギ群落としてまとめられているので、本群落の詳細な分布範囲はわからないが肱川を除く全ての河川に分布している。四国の河川の多くは、河床勾配が急であり、河口まで石礫の河原が続いており、本群落の立地が整っているといえる。 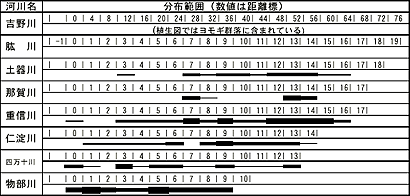 ■保全上の留意点および保全・創出に関する事柄 過酷な環境下に成立するため、人為的な攪乱には非常に脆弱である。また、人工的な群落の創出も非常に困難と思われ、現状を保全していくことが必要である。しかし、立地の富栄養化が進み、セイタカアワダチソウ、クズなどに占領されてきている。そのため、低水敷ではあるが、刈り取りなどの人為的な管理が必要となるかもしれない。本群落の保全、維持は今後の重要な課題となろう。 ■植物社会学上の位置づけ カワラサイコ−カワラヨモギ群集、カワラケツメイ−カラメドハギ群集や関東・中部地方に特有のカワラノギク−マルバヤハズソウ群集が報告されているが、四国地方のものは、カワラケツメイ−カラメドハギ群集に位置づけられる思われる。上級単位は、ヨモギ−カワラハハコ群団、ヨモギオーダー、ヨモギクラスである。 |
|
|