■コセンダングサーアキノエノコログサ群落
 |
 ■識別ポイント 前述のメヒシバ−オオクサキビ群落とよく似た組成、立地に成立するが、コセンダングサ、センダングサ、アキノエノコログサなどの夏型および冬型一年草が優占または混生することにより識別できる。立地は低水敷の護岸の隙間など、やや湿性から乾性な場所である。群落高はほとんどが1 〜1.5m 程度である。コセンダングサやセンダングサは、その果実の先に逆向きのトゲがあり、”ひっつき虫”としても有名である。また、アキノエノコログサはいわゆる”ねこじゃらし”で、夏から秋にかけて毛むくじゃらの穂が垂れることで見分けることができる。 ■構成種 構成種は3 〜25 種程度と立地環境により大きな差がある。平均は15 種程度である。キツネノマゴ、メヒシバ、ツユクサ、ヨモギなどが混生する。 ■成育立地の環境特性 適湿からやや乾燥した砂礫質の土壌に成立する。冠水または工事などの攪乱を受けた立地に先駆的に成立するほか、高水敷や護岸にも成立する。冠水頻度が低下したり、人為の影響が少なくなるとヨモギクラスやノイバラクラスの群落へ遷移すると考えられる。 ■生態的機能 生態的には、前述のメヒシバ−オオクサキビ群落と非常によくている。本群落はメヒシバ−オオクサキビ群落から遷移してきたものも少なくないと思われる。エノコログサ類などの種子は、スズメ、カワラヒワなどの鳥類の餌となる。 ■隣接する群落 水辺側ではヤナギタデ−オオイヌタデ群落など、陸域側ではヨモギ−メドハギ群落、ノイバラ群落などと隣接する。 ■四国での分布 肱川、仁淀川、物部川で広く確認されている。 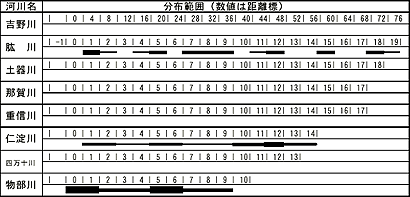 ■保全上の留意点 特に留意することはない。 ■植物社会学上の位置づけ コセンダングサ−アキノエノコログサ群集、アメリカセンダングサ−タウコギ群団、タウコギオーダー、タウコギクラス |
|
|