■メヒシバーオオクサキビ群落
 |
 ■識別ポイント 低水敷の砂質壌土の河原で、外来植物であるオオクサキビが成育し、メヒシバ、イヌビエ、ケイヌビエ、ノゲイトウなどの一年草が優占また混生することにより区分した。しかし、まとまった組成群や優占する植物にも違いがみられ、今後詳細な検討が必要な群落である。群落高はほとんどが0.5 〜1.2m 程度である。河川敷を造成した後すぐに侵入する植生である。秋〜冬季には優占種のメヒシバやオオクサキビが枯れ、薄茶色となるので群落を識別する手助けとなる。 ■構成種 構成種は3 〜25 種程度と立地環境により大きな差がある。平均は15 種程度である。キンエノコロ、コゴメガヤツリ、イヌビユ、エノキグサ、ヤハズソウなどの一年草の出現頻度が高いほか、ヨモギなどの多年草も混生する。 ■成育立地の環境特性 年に1 回程度冠水する半安定地、または安定し乾燥した高水敷でもごく近年に造成などの攪乱を受けた立地である。本群落は、改修や工事後の低水敷、高水敷にまず最初に成立する群落である。湿性な立地ではイヌビエ、ケイヌビエなどの優占度が高くなり、乾性な立地になるとメヒシバやノゲイトウ、ホソアオゲイトウの優占度が高くなる傾向にある。外来植物であるオオクサキビは適応する環境が広く、過湿地から乾性な立地まで広く成育する。将来的にはヨモギクラスやノイバラクラスの群落へ遷移すると思われる。 ■生態的機能 オオクサキビをはじめ本群落の構成種はほとんどが一年草であり、多くの種子生産を行う。それらが土壌中に埋土種子として生存しているために、造成後すぐに成立するものと考えられる。本群落が成立した後、増水などで冠水を受けるとしばらくは維持されるが、湿性な立地ではヤナギタデ−オオイヌタデ群落に、乾性な立地ではヒメムカシヨモギ−オオアレチノギク群落からヨモギ−メドハギ群落などに遷移すると思われる。 なお、本群落に混生するエノコログサ類などイネ科植物の種子は、スズメ、カワラヒワなどの鳥類の餌となる。 ■隣接する群落 水辺側ではヤナギタデ−オオイヌタデ群落など、陸域側ではヨモギ群落、セイタカアワダチソウ群落、ノイバラ群落などと隣接する。 ■四国での分布 ほとんどの河川で広く分布しており、いずれの河川でも改修工事などによる改変地の出現を示している。 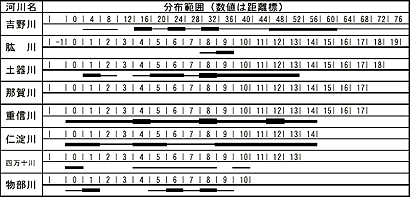 ■保全上の留意点 特に保全、留意する必要なない。前述したように、本群落が広く占めるところは過去1〜2 年の間に工事などによって改変を受けたことを現しており、自然な植生へ移行させるべきである場所を示しているともいえる。 ■植物社会学上の位置づけ 今回の区分では乾性な立地から湿性な立地までを含んで本群落にまとめたが、詳細な検討により、いくつかの群落に分けられる可能性もあり、今後の検討項目であろう。少なくとも湿性な立地の植生は、組成的にタウコギクラスにまとめられると思われる。 |
|
|