■ツルヨシ群落
 |
 ■識別ポイント 流水辺の砂礫地にツルヨシが優占し、大きな群落を作ることで識別できる。ツルヨシはヨシによく似るが、地表を這うように地上茎(地上走出枝:ランナー)が伸びること、流れのある水辺に成育することなどから識別できる。ツルヨシは多年生のイネ科植物で、匍匐するランナーの節から新たな芽や根を出して定着する。ランナーは1 年で平均4m 、最大で15m も伸び、冠水に対する耐性は高い。逆に地下水位の低い場所に伸びた地上茎は定着できない。地下水位が0.5m 以下あたりの立地に分布が集中する傾向がある。 ■構成種 構成種は平均10 種程度と少なく、ヨモギ、ギシギシ、セイヨウカラシナ、スイバ、ツユクサなど他群落との共通する種が多い。 ■成育立地の環境特性 流水辺の砂礫地に成立する。一般的には河川の中から上流域の石礫の河原の水際に多い。しかし、急な河床をもつ四国の河川では下流域まで分布を広げていることも少なくない。 ■生態的機能 ツルヨシがランナーを巡らすため、土壌の保全能力に優れる。通常の水位の時は、陸域はオオヨシキリやカワラヒワなどの鳥類、水中では稚魚の生息場となり、増水時には土壌保全や魚類の避難場所となり、生態的機能は多様である。 ■隣接する群落 上流域では水辺側でネコヤナギ群落と、下流から中流域では水辺側でヤナギタデ−オオイヌタデ群落と、陸側でヨモギ−メドハギ群落と共に成立することがある。 ■四国での分布 いずれの河川でも広く確認されている。物部川や仁淀川、四万十川などでは、下流域、河口域まで成立しており、河床勾配の急さ、河口域までの礫原の分布という河川形態の特性を指標している。 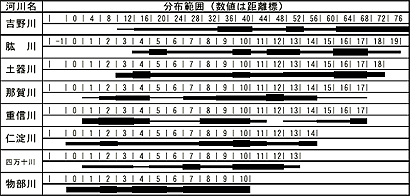 ■保全上の留意点 広範囲にわたり成立し、瀬、淵、交互砂州のある特有の河川景観を特徴づけることから、流水辺寄りのヤナギタデ−オオイヌタデ群落、砂礫地と共にセットで保全したい。植生護岸などに利用する際には、地下水位が0.5m よりも高い位置を中心に植栽する。 ■保全・創出に関する事柄 近畿地方整備局猪名川工事事務所では、低水護岸の前に人工基盤(コンクリブロックをネットに入れたもの)を形成し、ツルヨシの創出を図っている(写真右)。しかし、水位が人工基盤よりも下がってしまい、乾燥化によるツルヨシの衰退がみられる箇所もある。  ■植物社会学上の位置づけ ツルヨシ群集、クサヨシ−セリ群団、ヨシオーダー、ヨシクラス |
|
|