| ■ネコヤナギ群落 類似群落: カワヤナギ群落 参考群落: コリヤナギ群落
 |
 ■識別ポイント 河川の中上流部の水際の岩場などにネコヤナギが成育していることで識別できる。ネコヤナギは流水辺に成育する低木のヤナギである。早春に銀色の毛に包まれた花芽をみると容易に識別できる。カワヤナギはネコヤナギの後背側や下流部の安定した立地に成育する高木性のヤナギであるが、流水辺などではネコヤナギ同様、低木状で群落を形成する。コリヤナギは柳行李(やなぎごうり)や切り花の材料として栽培される低木のヤナギであり、葉が対生することが特徴的である。 ■構成種 いずれの群落も樹高は2m 程度である。流水辺近くでは共存する種が少なく単純な群落となるが、陸域に成立する群落内では、下層にヨモギ、ツルヨシ、ギシギシなどが10〜20 種が混生する。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 ネコヤナギは渓谷状の岩場の流水辺が成育の中心であるが、平坦な石礫の河原の最前線などにも成育する。岩の隙間に根を張り巡らして支えるとともに、増水、冠水にも耐えられるよう枝条は非常にしなやかである。カワヤナギはネコヤナギの後背ややや安定した砂礫質の低水敷などに成育する。いずれも河川の流水環境に適応した森林群落であり水辺から陸域へのエコトーンでも陸側の重要な植生であり、鳥類にかくれ場、陸上貝類などの生息の場として利用される。 ■隣接する群落 山付きなどでは後背にエノキ−ムクノキ群落やアラカシ群落に接する。河原ではツルヨシ群落などにつながる。 ■四国での分布 ネコヤナギ群落は那賀川、物部川を除く6 河川の中上流部を中心に確認されている。ネコヤナギ群落は密生せず、点々と成育することもある。そのため、那賀川や物部川の上流域の渓谷上にも分布している可能性はある。カワヤナギは仁淀川で1 地点だけ調査されているのみである。 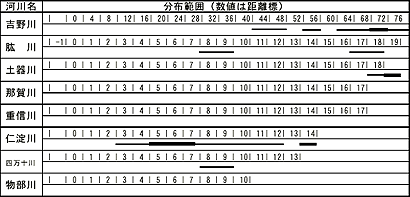 ■保全上の留意点 水際の岸に根を張って成育することから自然な低水護岸機能および上述した生態的機能を備えており、河川で果たす役割は大きい。渓谷上の植生は現状を維持すればよい。中流域のものについては現状を保全するとともに、多自然型の低水護岸に導入し、復元を図ることも有効である。 ■保全・創出に関する事柄 ヤナギ類は挿し木などにより、容易に増殖可能である。しかし渓谷などへの自然地形への移植は非常に困難であろう。低水護岸に植栽する場合は、乾燥が激しくならないよう水面からの高さに留意して、挿し木、株移植などが適していよう。 ■植物社会学上の位置づけ 低木のヤナギ林にはネコヤナギ群集があり、ネコヤナギ群団、コゴメヤナギ−シロヤナギオーダー、オノエヤナギクラスに含められている。 |
|
|