■キシュウスズメノヒエ群落
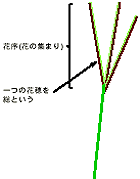 |
 ■識別ポイント 湾入部の止水域などの浅い水際にキシュウスズメノヒエが優占していることで識別できる。キシュウスズメノヒエは、アジアの熱帯地方原産のイネ科の多年生植物である。水面に茎を伸ばし、そこから茎が立ち上がり先に二股に分かれた花穂を出す(花序の総が2本出る)。近年は、これに似たチクゴスズメノヒエも各地で分布を広げており、キシュウスズメノヒエと混在して群落を形成することもある。チクゴスズメノヒエは花序の総が2 〜3 本であり(右上図参照)、植物に長い毛が多いことで見分けることができる。 ■構成種 群落高は0.5m 程度であり、ヤナギタデやミゾソバなど数種が混生する。また、キシュウスズメノヒエはヒメガマ群落などの構成種として、ヒメガマの下層などに群生する。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 過湿な砂質から泥質地に成立する。河川内のやや流れのある湾入部の水際などには、本来成育できる在来植物が少なかった。そのため、競合する種がなく、キシュウスズメノヒエがどんどん分布を広げたようである。トンボなどの水生生物や小魚に生息、かくれ場を提供している。 ■隣接する群落 ガマ、ヒメガマ群落、ヨシ群落やツルヨシ群落などに隣接する。 ■四国での分布 河口、下流部を中心に全ての河川で確認されている。肱川は下流部が山付きであること、中上流域でも止水環境が少ないことから、分布が少ないものと考えられる。 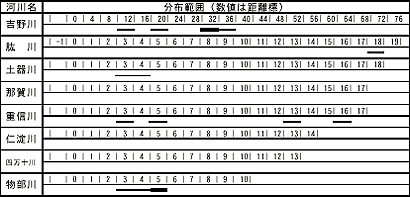 ■保全上の留意点 本種は外来植物であるため、重要性は低い。しかし、多様な水辺環境を形成している点では、生態的には価値がある。群落の保全ということよりも、豊かな水辺環境を保全するという視点でみるべきであろう。 ■植物社会学上の位置づけ キシュウスズメノヒエの優占群落は群集レベルでの位置づけはされていない。生育環境から上級単位はヨシクラスに所属すると思われる。 |
|
|