| ■シチトウ群落 参考群落: キショウブ群落
 |
 ■識別ポイント 外来植物であるシチトウ、キショウブが優占することで識別できる抽水性植物群落である。シチトウ(別名シチトウイ)はカヤツリグサ科の多年草で中国原産であり、畳表用に栽培されていたものの逸出(いっしゅつ)である。 キショウブはアヤメ科の多年草で欧亜大陸原産で、明治時代に観賞用に導入されたものである。 ■構成種 シチトウは一種で純群落を形成し、キショウブ群落はガマ、カサスゲなど5 種類程度からなる。 ■成育立地の環境特性・生態的機能 いずれも水湿条件は過湿な泥質地である。先に述べたガマ群落やヒメガマ群落と同様の環境であり、水生生物の生息場に利用される。 ■隣接する群落 陸側にヤナギ林、オギ群落など、水側にヨシ群落、ガマ群落、ヒメガマ群落などに隣接する。 ■四国での分布 シチトウ群落は、肱川、仁淀川の下流、河口域で、キショウブ群落は土器川の低水敷にできた過湿地に成立している。 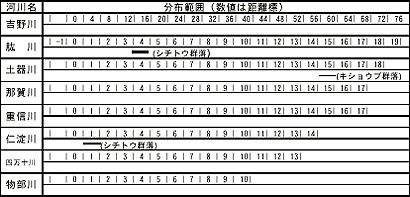 ■保全上の留意点 いずれも外来植物であり、植物、群落としての重要性は低い。しかしながら、それらが成育する立地は河川独特の水湿環境であり、ヨシ群落、ガマ群落、ヒメガマ群落など自然植生が成立できる立地である。そのため、その場所の保全および在来種による自然植生への転換により、自然性を高めることができる。 ■植物社会学上の位置づけ 外来植物であるシチトウ、キショウブの優占する群落は群集レベルでの位置づけはされていない。成育環境からヨシクラスに含められると考えられる。 |
|
|