■クサヨシーセリ群落
|
 ■識別ポイント 水際や低水敷の適湿〜過湿地に、クサヨシが優占することにより識別できる。クサヨシはイネ科の多年生草本であり、草丈は1.5m 程度で、地下茎を伸ばして群生する。豪壮な茎を持たないクサ状のヨシという意味である。5月頃に淡い薄褐色の花穂が群生することで、見分けることができる。 ■構成種 立地が過湿地であるのでセリ、ミゾソバなどの水辺の種の他、場所によってはヨモギ、カラスノエンドウの路傍雑草なども混生する。構成種数は、8〜15 種である。また、クサヨシはヨシ群落、ガマ群落、オギ群落などの下層にも群生することがある。 ■成育立地の環境特性 止水または緩い流れのある過湿な環境で、土壌はやや富栄養な粘土質の立地である。傾斜がなく平坦な河床や低水敷で、常に冠水している場所からやや適湿な場所まで成育範囲は広い。群落は増水によりしばしば冠水する。 ■生態的機能 水辺から陸域へのエコトーンを形成する群落であり、トンボ類やカエルなどの両生類などにとっては、重要な生活の場となっている。 ■隣接する群落 過湿地ではヨシ群落やガマ、ヒメガマ群落など、陸域にはオギ群落、ヤナギ林などに隣接する。 ■四国での分布 下記の4 河川で確認されているが、どれも小規模である。四国の河川は、河床が礫や砂でできているものが多く、本群落の潜在的な立地が少ないのかもしれない。 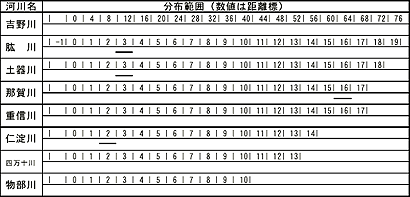 ■保全上の留意点 生態的な価値、整然とした草原としての景観の美しさから、保全しておきたい群落である。造成後の低水敷などに復元する目標植生として適した群落である。 ■保全・創出に関する事柄 過湿な水環境に成立する自然植生として、生態的に価値があり、環境全体の保全または創出が必要となろう。クサヨシに関する創出例はないが、地下茎を持つので、掘り取り株を移植することで増殖は可能であろう。群落が改変されるときには表層土壌を採取し、類似した湿性環境へまき出すことにより、群落、環境の創出が可能となるかもしれない。 ■植物社会学上の位置づけ クサヨシ−セリ群集、クサヨシ−セリ群団、ヨシオーダー、ヨシクラス |
|
|