■メダケ群落
 |
 ■識別ポイント 低水敷および高水敷において大型のササのメダケが優占することで識別できる。群落高は2 〜6m に達する。非常に密に繁茂し、河川の縦断方向と平行に群落を発達させる。メダケは稈から3 本以上分枝することで見分けがつく。 ■構成種 構成種は数〜30 種程度、平均は15 種程度である。おもに、ノイバラ、ヤマノイモなどノイバラクラスの種やヨモギ、ヒナタイノコズチなどヨモギクラスの種が多い。 ■成育立地の環境特性 低水敷から高水敷まで成育できる適応範囲は広い。土壌条件は肥沃な砂質壌土である。不定期な冠水などの攪乱により持続していると考えられる。 ■生態的機能 メダケは蝶類のコチャバネセセリやヒカゲチョウの食草となるほか、スズメなどの塒となることもある。また、メダケは地下茎が発達するため、自然堤防の植生として土壌保全機能は高い。物部川の上流部左岸ではメダケが帯状に発達し、自然堤防の一つの典型的な景観を示している。 ■隣接する群落 水辺側ではヨシ群落などと隣接するが、直接水辺に接することも多い、陸域側ではクズ群落、ノイバラ群落、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。 ■四国での分布 いずれの河川でも確認されており、縦断方向の分布範囲も広い。 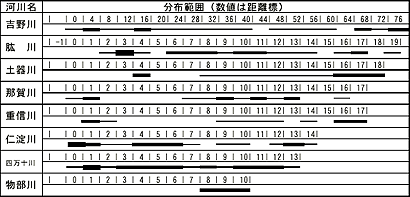 ■保全上の留意点および保全・創出に関する事項 土壌保全機能が高いことから、治水上問題のない限り保全することが望ましい。また、四万十川では多自然型川づくりが進められており、左岸の坂本背割箇所では張り出した低水敷にメダケを株ごと移植し、植生による護岸、緑化を行っている。 ■植物社会学上の位置づけ メダケ群集、センニンソウ−エビヅル群団、クズ−トコロオーダー、ノイバラクラス。 |
|
|