■アキグミ群落
 |
 ■識別ポイント 低水敷や低水護岸尻などにおいてアキグミが優占する低木林である。アキグミの葉は、長い楕円形で裏が銀色に光っており、すぐに見分けがつく。また、秋には紅色の小さな実がなり、食べるとおいしい。群落高は2 〜4m と低い。 ■構成種 構成種は15 〜30 種程度、平均は20 種程度である。おもに、ノイバラ、ツルウメモドキ、スイカズラなどのノイバラクラスの種やススキ、コセンダングサなどの出現頻度が高い。 ■成育立地の環境特性 砂礫質の立地に多く、常時は乾燥気味の砂礫質土壌に多いようであるが、詳細は検討を要する。本群落は、自然な状態であれば、数年に一度の冠水により維持されると思われる。攪乱頻度が低下するとアカメガシワ−ヌルデ群落などへ移行する。 ■生態的機能 アキグミはやや乾燥した砂礫河原でも群落を形成することができる。また、果実は鳥類の餌となる。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落、オギ群落など、陸域側ではクズ群落、ノイバラ群落、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。 ■四国での分布 吉野川、那賀川、四万十川、物部川において確認されている。特に、那賀川では砂礫の河原に大面積で分布しており、那賀川を特徴づける植生となっている。 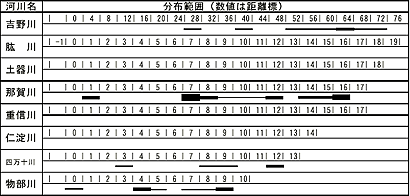 ■保全上の留意点および保全・創出に関する事項 河川内の樹林環境として貴重な存在であり、治水上問題のない範囲で保全することが望まれる。四万十川では多自然型の護岸として、河口域左岸の下田箇所で、低水護岸上のアキグミを植栽している。現在、活着し帯状の群落を形成している。 ■植物社会学上の位置づけ アキグミの優占林の群集は報告されていない。成立状況からノイバラクラスに近いと考えられる。 |
|
|