■アカメガシワーヌルデ群落
 |
 ■識別ポイント やや乾いた低水敷に発達する夏緑樹(落葉広葉樹)の低〜高木林であり、アカメガシワまたはヌルデが優占することで識別できる。群落高は2 〜5m である。ヌルデはウルシ科の植物であり、樹液などがつくとかぶれるおそれがあり、注意が必要である。 ■構成種 構成種は15 〜30 種、平均は20 種程度である。ヨモギ、セイタカアワダチソウ、イタドリなどの雑草種(ヨモギクラス)の出現頻度が高いほか、ネムノキ、エノキなどの夏緑樹も混生する。 ■成育立地の環境特性 ほとんど冠水しない肥沃な低水敷に成立する。冠水や改修などの攪乱後に生じた代償植生であり、放置すればエノキ−ムクノキ群落へ移行すると思われる。 ■生態的機能 林縁性の鳥類や昆虫類の生息環境となっている。河川では少ない森林植生であり、低木層、草本層といった階層構造をもつため、生態的な環境、機能は草本植生と比べると多様である。増水時には魚や貝類など避難場所に利用されると考えられる。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落、オギ群落など、陸域側ではマダケ群落などの各種竹林、クズ群落、ノイバラ群落、エノキ−ムクノキ群落、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。 ■四国での分布 ほとんどの河川で確認されているが、分布範囲は点在している。 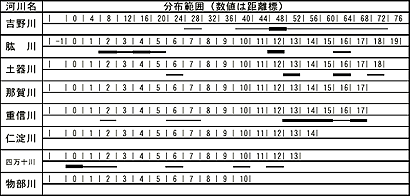 ■保全上の留意点 河川内に残された本群落は、樹林環境として貴重な存在であり、治水上問題のない範囲で、できる限り保全することが望まれる。 ■植物社会学上の位置づけ 伐採跡の先駆植物群落には、タラノキ−クサイチゴ群集があり、それと同類の植生と考えられる。アカメガシワ−クサギ群団に含められるが、オーダー、クラスの位置づけは明らかになっていない。 |
|
|