具体的な進め方」を検討するとしたら・・
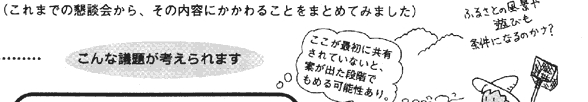
計画条件は何か?
どんな条件を満たす案であればみんなが納得できるのだろうか。 治水、利水、環境(生物環境、親しめる水辺、景観などを含む)の条件を、具体的にどのように設定したらよいのかを、話し合う必要がある。
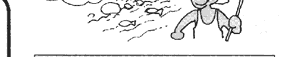
・洪水が起きても心配のない、分水も心配のない案なら可動堰でなくてもよいのでは。
・川を大切に、命と安全、利水が必要というのは共通している。
これまでは、建設省案しかなかったから○か×になってしまったのではないか。もし、それに対抗する市民案がひとつ出てきても、○か×になる。もっとたくさんの選択肢が出されて、比べていけるとよいのではないか。
・多数の案を作成して選択する
・日本中の工学者に検討してもらう
・堰の形などを一般公募 ・コンペ(設計競議)を開催する。
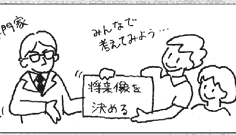
建設省が住民の提案を受ける、行政が選んだ審議委員会で検討する、というのではない新しい評価システムがつくれないか。案の評価基準、評価委員の構成などを、納得のいく形にしていく必要がある。このシステムがないと、市民団体の案も結局は建設省に対して提言するしかないのでは?
・主体は市民、専門家は補佐。
・行政は、市民案を法的、財政的に研究
・専門家として、学者だけでなく、漁師さんなどにも入ってもらう
案づくりや案の選択過程に、できるだけ流域の多くの人の参加できる方法を考えていく必要があるのではないか。
・徳島市だけでなく、流域市町村や氾濫源に住んでいる人の意見も聞くべき。
・みんなが納得できる情報公開をする。
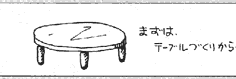
★まずは、共通のテーブル自体の運営方法についての案が必要
・共通のテーブルの運営は、誰が行なえばいいのだろう?
・専門家には、どのようにかかわってもらえばいいのだろう?
・共通のテーブルでの検討をオープンにし、理解し参加してもらう方法は?
・中立.公平な第三者が必要ではないか?
・市民が主体、学者はその補佐。