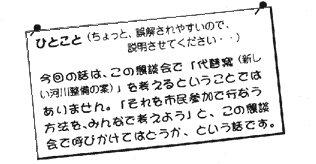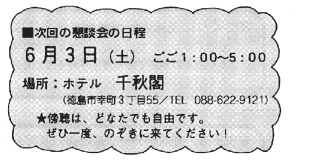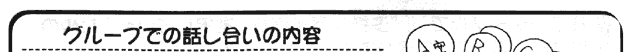
・この提案はよいと思う。でも「代替案」でなく「よりよい案」とかの方がよい。
・広く、利害関係のある人から話しを聞く。
・視野を広げると、利害関係はもっとほかに出てくる。
・テーブルを作るだけではなく合同調査もやってみては。
・最後に決定する人は誰か?県民投票か?でも多数決で解決できる問題か?
◆第2グループ
・意見の共通している点を整理したことは、評価できる。共通 のテーブルとなり得る。
・建設にかかる費用も考えないといけない。
・「代替案」にかわる名称として、「コンペ」が良いのでは。
・設計コンペを一般公募でやる価値はある。一般市民から見て、建設省だけがやっているのではないことがはっきりする。
・(可動堰案は)治水、利水上問題がないと考えている人たちもいる。
・前提として、老朽化などについての勉強をしたい。
・誰が調査して、誰が判断するのか。それが難しい。
◆第3グループ
・共通の話題から入るといのはよい。あとはその場にくるかどうかだ。
・イデオロギーの問題、政治の問題になっているところがむずかしい。
・「よりよい案づくり」の考え方の根拠はわかるはず。共通の話題なら出せるのでは。
・まずはわれわれがもっと勉強しなくてはいけない。
・ 有効な話し合いをするには、「代替案」をキーワードにしたテーブルが有効(これしかない)
・ 「代替案」ではなく 「いい解決のための案」ということにしたらどうか。
・案の中には、「第十堰をそのままにしておく」というものも入るのか?
・市民レベルのアイデアを、プロのコンペ案に盛り込んでもらえるとよい。
・懇談会でも、いい解決をするための条件を提案する必要がある。 ・われわれに治水とは?利水とは?ということが理解できているのか。
◆第5グループ
・「案づくり」の前提として、 現状を共通認識として共有する必要があるのでは。
・代替案の基本理念は、 人の命と財産を守ること。 ・ 無駄なものを造らないというのも、大事。
・ 市民から代替案のアイディアを出してもらい、建設省が技術的検討をしてまとめ、専門家が技術面 の評価する。
・ 最終決定は多数決ではいけないが、十分に検討して、そうせざるを得ないだろう。
・ 多数決としても、少数派が納得できるような決め方としたい。