■シオクグ群落
|
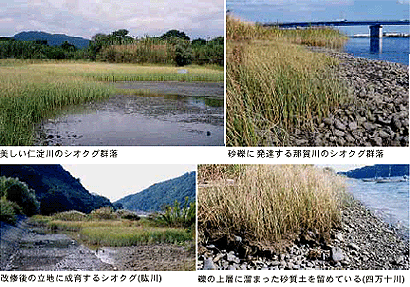 ■識別ポイント・構成種 河口部の塩湿地や冠水域にシオクグが優占していることで識別できる。群落高は50cm程度で、このような立地に群生するスゲ属の種は四国ではシオクグしかなく、識別は容易である。ハマサジ、ウラギクが低被度で混生する程度でほぼ純群落を形成する。 ■成育立地の環境特性 潮の干満の影響を受ける河口域の低水敷や塩湿地である。砂質土を好むが那賀川のように礫原に砂が溜まった立地にも成育する。また造成後の立地にも成育し、復元能力は高そうである。 ■生態的機能 干潟環境に成立しており、冠水時には魚類やカニなどの隠れ場、すみ場に利用されるなど、生態的な機能は高い。また、地下茎を密に張り巡らすことから、土壌保全能力も高い。 ■隣接する群落 陸側にはアイアシ群落またはヨシ群落に接する。 ■四国での分布 前ページの写真にあるように、仁淀川の河口部の群落は極めてよく発達しており、美しい景観を示す。肱川では、細長く点々と分布する程度である。また、今回の踏査により吉野川、那賀川の河口域で本群落を確認した。 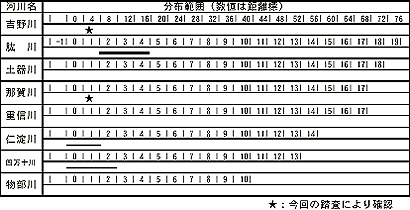 ■保全上の留意点 塩沼地、海浜という特殊な環境に成立する群落として、魚介類に寄与する生態的価値は高い。また、前述したように繁茂による土壌の保全能力にも優れており、成育地の環境全体の保全により、群落を維持することが必要である。 ■保全・創出に関する事柄 近畿地方整備局姫路工事事務所により加古川でシオクグの移植事例がある。移植の耐性は強く、土壌ごと根茎を移植する方法や播種による増殖を試みている。 ■植物社会学上の位置づけ シオクグ群集、ヨシ群団、ヨシオーダー、ヨシクラス |
|
|