■ナガミノオニシバ群落
 |
 ■識別ポイント・構成種 河口域の干潟、砂浜でナガミノオニシバが優占することで識別できる。ナガミノオニシバはイネ科の多年草で匍匐茎を延ばしてマット状に成育する。構成種は少なく、ウラギク、ヨシなどが低い被度で混生する。構成種数は3 〜5 種。 ■成育立地の環境特性 水湿条件は干潟または干満の影響を受ける河口域であり、立地は砂〜礫質である。干満の影響を受ける立地で中でも、もっとも高い立地にある。 ■生態的機能 干潟に成立する植生として、干潟、砂浜の生物に対して、環境の多様性を高めている。 ■隣接する群落 水辺側にハマサジ群落が隣接する。陸側にはシオクグ群落、アイアシ群落、ヨシ群落などにつながる。 ■四国での分布 河川水辺の国勢調査では四万十川からの報告のみであるが、今回の現地踏査により、那賀川、吉野川、土器川(小面積)、重信川(小面積)の河口域でも確認した。 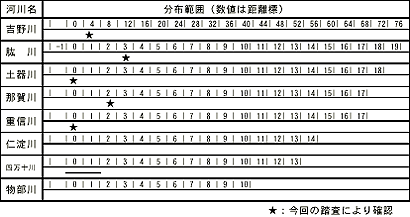 ■保全上の留意点 干潟、海浜という特殊な環境に成立する群落であるため、群落が成立している環境全体の保全により、本群落の維持を進めていく必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 ナガミノオニシバを対象にした保全・創出の事例はない。上述のように、個体の保全でなく、干潟、海浜の環境全体を保全する必要がある。ナガミノオニシバの増殖は、株の移植が効果的であると思われるが、十分な試験、調査が必要である。 ■植物社会学上の位置づけ ナガミノオニシバ群集、ナガミノオニシバ群団、ナガミノオニシバオーダー、ウラギククラス |
|
|