■セイタカヨシ群落
|
 ■識別ポイント 低水敷において大型イネ科植物のセイタカヨシが優占することで識別できる。群落高は3.5m に達する。セイタカヨシは一般にヨシよりも大型で、葉が斜め上に向いてつく。また、冬でも枯れずに葉は緑色をしているので、遠方からの識別も容易である。 ■構成種 構成種は10 種程度であり、カナムグラ、ヘクソカズラ、ヨモギなどが混生するが、ヨシクラスの種はほとんどみられない。 ■成育立地の環境特性 適湿な砂質土で冠水頻度の低い低水敷に成立する。水面からの比高は約1m 程度である。優占種のセイタカヨシが密生するため、遷移はほとんど進まないが、冠水頻度が低下すると長期的にはエノキ−ムクノキ群落などへ遷移すると考えられる。 ■生態的機能 形態的にはヨシに類似しているため、オオヨシキリなどの鳥類の営巣環境として機能するほか、冬季には鳥類の塒(ねぐら)としても利用されている。また、地下茎が発達するために、土壌の保全能力にすぐれる。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落、オギ群落など、陸域側ではクズ群落、カナムグラ群落、ノイバラ群落、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。 ■四国での分布 重信川でのみ確認されているが、面積は小さい。 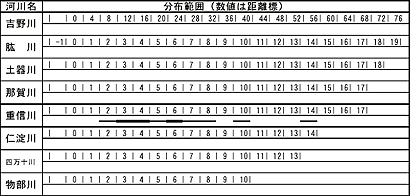 ■保全上の留意点 前述したとおり、河川のヨシ原に特有なオオヨシキリなどの鳥類の営巣環境となっている可能性があるため、整備にあたっては事前に生物の生息状況を調査する必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 セイタカヨシの種子の稔実率は低く、播種による復元は困難である。また、地下茎からの再生もあまりよくないことから、移植・復元を行う際には、移植試験をおこなうなど、事前に手法を検討する必要がある。 ■植物社会学上の位置づけ ヨシクラスに含められているが、検討を要する。 |
|
|