| ■マダケ(竹林)群落 類似群落: モウソウチク群落、ハチク群落、ホテイチク群落、ホウライチク群落
|
 ■識別ポイント マダケ、モウソウチク、ハチクなどの優占する竹林であり、離れた場所からでも容易に識別できる。群落高は4 〜17m と立地環境により大きな差がある。なお、ホテイチク、ホウライチクはやや低木性の竹であり、マダケ群落やモウソウチク群落などとは相観は異なる。 ■構成種 構成種は数〜60 種程度と立地環境により大きな差がある。おもにヤブラン、ナワシログミなどのヤブツバキクラスの種、ビワ、チャノキ、シュロ、ナンテンなど人家から逸出した種、エノキ、ムクノキなどが出現する。 ■成育立地の環境特性 ほとんど冠水しない安定した湿潤で肥沃な立地である。タケ類の多くは護岸や竹材の利用を目的として植栽されたものである。 ■生態的機能 植栽起源の群落であり、自然性は低い。また、タケ類が密生する群落では、林内が暗く、他の植物の成育が困難である。ただし、地下茎が発達するため、土壌保全機能は高い。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落など、陸域側ではオギ群落、ヨモギ群落、セイタカアワダチソウ群落、耕作地などと隣接する。 ■四国での分布 いずれの河川においても確認されている。とくに、吉野川、肱川、仁淀川では広く分布している。吉野川では、竹林は水害防備林として積極的に植栽されてきた。 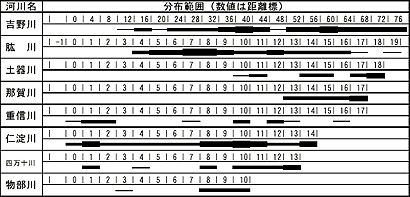 ■保全上の留意点 自然性は低いが、土壌保全機能が高いため、治水上問題のない限り、立地を保全することが望ましい。また、先人達の治水の努力を今に残す景観であり、歴史的、文化的な価値も高く評価されるべきであろう。 ■植物社会学上の位置づけ 植栽起源の群落のため、位置づけされていない。 |
|
|