■ハマサジ群落
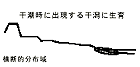  |
 ■識別ポイント・構成種 河口の干潟などの塩沼地に、ハマサジが群生することにより識別できる。ハマサジはイソマツ科の多年草であり、さじ型の根生葉(こんせいよう)が座布団状に成育することですぐ見分けがつく。土器川や重信川ではハママツナやネズミムギがわずかな被度で混生し、那賀川ではウラギク、イソヤマテンツキなどが高被度で混生する。 ■成育立地の環境特性 礫質から砂礫質の干潟に成立する。潮の干満により成立する干潟に成育する。満潮時には完全に冠水する。 ■生態的機能 ハマサジ群落が成立する干潟は多くの底生動物が生息しており、シギ類などの鳥類の重要な餌場となる。特に重信川の干潟は面積が広く四国でも有数の野鳥観察場となっている。 ■隣接する群落 高位面にはヨシ群落、低位面にはハママツナ群落、ホソバノハマアカザ群落、ナガミノオニシバ群落などに接する。 ■四国での分布 群落としては、重信川、那賀川、土器川に分布する。重信川、那賀川のハマサジ群落は極めてよく発達しており、四国でも貴重性が高い。土器川の群落は2回の国勢調査の間に面積が縮小したようである。また、肱川にはハマサジは成育するものの、成育する立地が狭いために群落を形成するまでには至っていない。 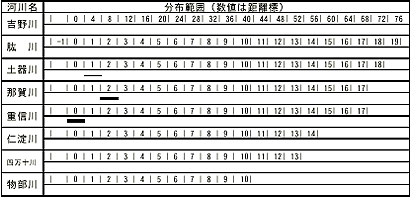 ■保全上の留意点 干潟という特殊な環境に成立する群落であるため、干潟環境全体の保全による本群落の維持を進めていく必要がある。 ■保全・創出に関する事柄 ハマサジを対象にした保全・創出の事例はない。ハマサジそのものの保全はもとより、それ以上にハマサジが群落として成立している干潟環境が重要である。干潟にハマサジを増殖するときは、株の移植が効果があると思われるが、十分な試験、調査が必要である。平成9 年には松山工事事務所では、表土を利用したハマサジやコウボウムギなどの復元を行っている。 ■植物社会学上の位置づけ ハマサジ群集、ナガミノオニシバ群団、ナガミノオニシバオーダー、ウラギククラス |
|
|