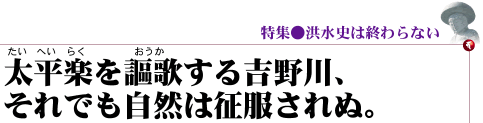
| 大正元年洪水の凄まじさ |
| 大正元年9月23日。吉野川の災害史上に今も生々しく残る「大正元年洪水」が流域を襲いました。南海上から徳島の海岸部をかすめて通った台風が阪神地区に上陸し、徳島の最大風速は北西の風16・7m/sにすぎなかったが、徳島の降水量は551mm。台風最接近時には津波のような大波が打ち寄せ、高潮被害も発生しました。徳島の大平野は、”見渡す限り濁水満 々“で、一面泥の海と化していました。高いところでも床上浸水、低いところでは家屋が流され、屋根に登ったまま海に流されて行く人もあったと伝えられています。死者81人、行方不明14人、家屋全壊426戸、床上浸水26,708戸。これほど浸水地域の広い記録的な大洪水は、吉野川流域ではこれ以降おこっていません。 |
| あちこちに残る爪痕 |
| 北島町のD宅の納屋の土壁には、「大正元年洪水」の痕跡が今も残っています。その痕跡は、裏の水田から3・9メートルにもなることが測定されています。 山川町には、岩津から下流の堤防の骨格をつくりあげる吉野川第一期改修の記念碑があります。傍らに立っているのは、改修途中にやってきた「大正元年洪水」の痕跡を示した石柱。高さは記念碑の地盤から約3・3メートルもあり、この洪水がいかに大規模であったかを伺い知ることができます。 その他、藍住町のB宅の土壁にも浸水の痕が見られます。こうした「大正元年洪水」の凄まじさを物語る爪痕は、今でも中下流域のあちらこちらにくっきりと残っています。 尚、石柱には8尺7寸という刻字があります。 |






