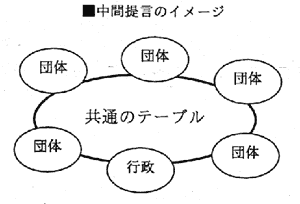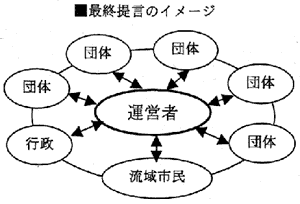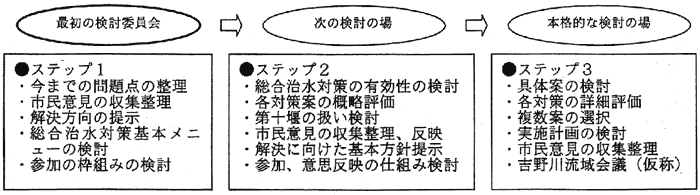| ■総合治水・市民参加検討委員会設置(案) |
現在、第十堰に関するいくつかの市民提案などがなされるようになっており、これらの提案を含め、多くの市民の意見を受け止められる「場」なり、「機関」を必要としている。
最初の「受け皿」を用意して、その「受け皿」を通じて、各団体との意見交換や公開討論会などを積み重ねることが当面必要と考えられる。多様な意見の「受け皿」として機能するためには、第十堰に関わる団体等の当事者ではなく、中立的な第三者による運営が望ましいと考えられる。 |
|
(1) |
検討委員会の性格(従来の審議委員会との違い) |
|
- 従来の「審議委員会」等のように、事業者が立案した計画の妥当性を判断したりする場とはしない。意思決定の場でもない。
- 検討委員会は、様々な市民(団体)意見を収集整理し、それらの意見を反映した「独自の提言」を創り出す。
- 検討委員会としての提言を行政機関や市民に提示し、豊かな市民参加、よりよい計画づくりをサポートする役割を果たす。
|
| (2) |
検討委員会の主な役割 |
|
- これまでの経過や問題点を整理し、検討すべき課題を提示する。
- 団体や市民の意見を集約し、課題を整理する。
- 問題解決に向けた基本方向や市民参加の枠組みについて提示する。
- 総合治水対策の基本的なメニューについて検討し、提示する。
- 「次の検討の場」や「次の検討課題」を提示する。
|
|
(3) |
検討委員会の構成 |
|
- 様々な意見を収集整理するという性格から、第十堰問題に直接関わる団体代表や行政関係者ではなく、第三者的な立場の人が望ましい。
- 異なる意見に耳を傾けることができる人材、中立的な立場で議論できる人材、バランス感覚のある人材、問題解決への意欲のある人材など。
- 公共事業、市民参加、総合治水対策、環境問題など、第十堰問題に関連する分野の人材をバランスのよい形で構成する。
- 一般市民、学識経験者、NGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)などが考えられる。
- 円滑な議論ができる適切な人数とする。
- 課題が多岐に渡るため、必要に応じて複数の専門部会等を設置することも考えられる。
- 議題の検討や討論内容の整理、資料作成などを行う運営委員会を設ける。
|
|
(4) |
委員の選定方法 |
|
- 全国的NGO(非政府組織)NPO(非営利組織)や第十堰に関わる市民団体などから推薦を受けることが考えられる。
- 事前に選定方法等について団体や市民からの意見を募り、選定方法を検討する。
- 誰が選定するかということについては、全国組織(NPO・NGO)等の代表と設置主体(行政)で構成する選定委員会を設けることが考えられる。
- 選考過程や選考基準等について、市民意見を可能な限り反映する。
|
|
(5) |
委員会の運営方法 |
|
- 設置者(行政)は、委員会の自由な議論や提案を保証する。
- 委員会をサポートする運営委員会(事務局)については、委員会で検討するものとするが、行政関係者だけでなく第三者が加わることを検討する。
- 委員会の議論は、委員の提案を軸に行うものとする。
- 委員会には、事業者側の責任者が必ず出席し、議論のプロセスの各段階で、意見や提案が意思決定に反映されるようにする。
- 委員会での議論は、独自の広報手段を通じて、広く市民に知らせる。一方的な広報ではなく、双方向のコミュニケーションが図れるよう工夫する。
- 広く市民的な討論が行われるよう、公開討論会等を適宜開催する。
|
|
(6) |
検討委員会立ち上げまでのプロセス |
|
- 検討委員会を立ち上げる場合は、事前に市民意見を収集整理する取り組みを行う。
- とりあえず、立ち上げまでのコーディネーターを選定し、市民団体との意見交換や公開討論会などを積み重ねることが考えられる。
- 設置主体については、河川管理者と関係自治体が協議し、市民意見もふまえて判断する。
|