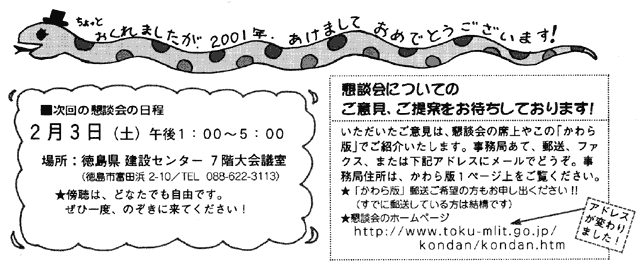|
|
 |
| |
| 住民参加や合意のあり方について |
| ・ |
建設省が行政責任を負うのは明確なことで、それにどう市民が参加するのか、建設省の下部機関では審議委員会と同じことになり、独立した機能をどうつくるのかが重要だ。合意形成のための組織づくり、構成メンバーの選考も難しいと思っている。大いに議論すべきことである。 |
| ・ |
(この問題に)住民投票はなじまない。審議会形式がよい。コンペでアイディアを集め、それを専門的に広げていけばよい。案をコンペで求め、世界的大家に決めてもらう方法を提案したい。 |
| ・ |
今度の事業主体は建設省だが、吉野川に関連する事業主体として農水省や水資源開発公社もある。建設省の場合、新河川法の規定があるが、他の事業主体に対しても市民の声を活かす方法を考える必要がある。 |
| ・ |
いろんなテーブルをつくってほしい。また、その組織図の中で、建設省や専門家の位置づけが明確になることが重要で、テーブルへの各団体のコミットの仕方、意見がどのように反映されるのかが見えてこないといけない。 |
|
|
 |
|
 |
注1:訪問は昨年8/29〜9/30の間に行われました。
注2:質問項目としては、共通して以下の点を伺いました。
1.団体の考え方やこれまでの活動について
2.問題解決のため、共通のテーブルで話し合うことについて
3.話し合いの障害について
4.話し合いのテーブルにつくための条件について
5.問題解決のためのスタートラインについて
6.問題解決のための場の構成やテーマ、運営方法について
7.住民参加や合意形成のあり方についての提案
8.懇談会や中間提言について
*「かわら版」紙面では項目を整理してまとめてあります。
|
 |
|
 |
| |
| 懇談会と懇談会の中間提言について |
| ・ |
懇談会が間に入って、相手の考え方を聞いて、まとめてくれるのはありがたい。中間提言については内容を見ていない。 |
| ・ |
懇談会は私たちの意見が無視されてできた団体であり、受け入れがたい存在である。呼びかけがあったとき見解を送ったが、無視された。認めるわけにはいかない団体であり、本来なら見解を述べる義理もない。懇談会は建設省がスポンサーであり、建設省の意見かなと思って、中間提言を見ている。新河川法に則って、建設省が懇談会のメンバーを利用しているのではないかと思っている。中間提言でいろんな意見が出ていることは認識したが、懇談会にどうこう言うつもりはない。 |
| ・ |
二分されている民意をまとめるのは本来、我々行政の仕事だが、懇談会に頑張ってもらいたい。 |
| ・ |
反対派に呼びかけても、参加しないときのテーブルづくりを、懇談会はどうするつもりか。 |
| ・ |
懇談会がやろうとしていることは、現状を打開するために考えられる最もよい方法と思われる。 |
| ・ |
懇談会のメンバーには敬意を払うが、先ずは県や建設省にテーブルができる状況づくりを求めるべき。懇談会は自前のテーブルを作るつもりか。私たちは、懇談会は建設省の呼びかけでできたのだから、(中立ではなく)建設省寄りと見ている。 |
| ・ |
懇談会については新聞記事程度の認識しかない。建設省が立ち上げたので、建設省寄りとの印象を抱いてきたが、よく分からない。
市民の声なき声を吸い上げることが大切-その方法の研究をしてほしい。反対派や賛成派の議論に、一般市民はついていけない。また建設省がどのように市民の声を計画に位置付けるのかが重要。懇談会が責任を持って、建設省や県にこの点を訴えてほしい。 |
|
|
 |
|
 |
|