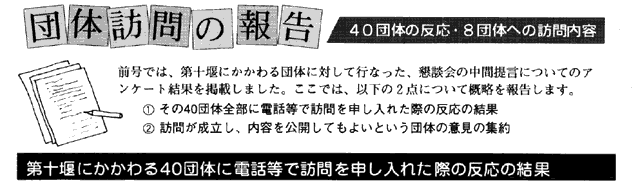
| 訪問に応じていただいた団体 *団体としてでなく個人として答えていただいた団体役員の所属する1団体を含む (団体名は伏せる) |
13団体 | (あいう順)板野郡農業協同組合/洪水から、いのちとくらしを守る住民の会/佐野塚・第十堰を考える会/第十堰改築事業促進連絡協議会/第十堰建設促進期成同盟会/第十堰撤去・可動堰建設に反対する石井町民の会/徳島環境と公共事業を考える会/(社)徳島経済同友会/徳島県商工会連合会/徳島県中小企業団体中央会/徳島商工会議所(第十堰署名の会)/吉野川土地改良区 |
| 訪問できなかった団体 | 20団体 | (断られた理由)
・懇談会を認めていない・・・11団体 ・特に意見がない、関連団体と同じ意見である ・・・9団体 |
| 連絡がとれなかった団体 | 7団体 | ・解散している・・・2団体
・電話連絡がとれない・・・5団体 |
| 訪問に応じていただいた13団体のうちの8団体の意見を以下に要約します。 団体名の公開に応じてくださったのは、板野郡農業協同組合、第十堰撤去・可動堰建設に反対する石井町民の会、第十堰建設促進期成同盟会、徳島商工会議所(第十堰署名の会)、吉野川土地改良区、佐野塚・第十堰を考える会の6団体です。2団体は、団体名の公開を希望されませんでした。 * 紙面の関係で訪問記録を全文掲載できませんので、項目別にご意見を抜粋し、団体名を伏せて掲載します。 |