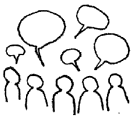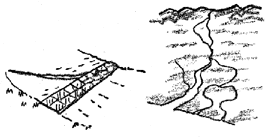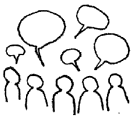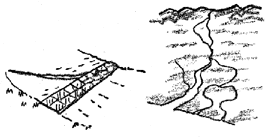| ■この懇談会の役割とは |
| 吉野川の問題は、「吉野川を大事に思う人たち(徳島の人たち)」で解決策を検討すべきと考えます。したがって、この懇談会は、皆さんが主役です。皆さんからの積極的な提案をベースにした話し合いを通
じて問題解決に向けた何らかの方向性が得られることを期待しています。私が考えているこの会の目的は、 |
|
1、 |
第十堰の取り扱いを中心に今後の吉野川のあるべき姿(将来像)、その実現方法や役割分担などに関して、多くの人たちの意見を反映したいと考えていますが、では、どのような仕組で意見を集約していくかという具対策がないのが現状です。したがって、この懇談会では、そのための方法論(土俵の作り方、対話のルール、参加者の選定方法、意見の検討方法など)を検討し提案します。 |
|
2、 |
さらに、この懇談会で示された意見集約の方法に基づいてより多くの人たちが参加した「次の対話の場」の実現に向けた取り組み(多くの関係者への働きかけなど)を行います。 |
| ■建設省徳島工事事務所の基本姿勢は |
|
・ |
皆さんの意見に耳を傾けることを基本とし、一参加者として誠意を持って話し合いに参加します。 |
|
・ |
さらに、この懇談会で何らかの方向性が示された場合、その実現に向けて誠心誠意努力します。 |
| ■この懇談会の運営はどうするのか |
|
・ |
この懇談会での合意は、参加者が対等の関係の中でそれぞれの意見の趣旨を尊重しつつ、極力全会一致を目指すべきものと考えます。 |
|
・ |
参加者が自主的に運営することが理想で、運営方法なども、参加者に決定していただきたいと考えます。 |
|
・ |
「皆さんの中から互選によって進行役や運営委員(世話人)を選ぶ」「徳島にゆかりがあり川づくりにも知識を持っている中立公平な第三者に委ねる」などの方法が考えられますが、運営主体や運営の方法などが決定されるまでの間は、河川行政に関する知識や複雑な問題の論点を整理するための専門的なノウハウを持った経験豊かな中立公平な第三者に手伝ってもらうことも一案であると考えます。 |