 |
|
|
 |
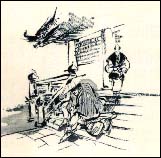 |
 |
駅路寺は、蜂須賀家政が慶長3年(1598)、街道をゆく旅人の便を図るために、阿波国内の主要街道沿いにある8つの寺院を宿泊施設として指定したもので、阿波独特の制度です。伊予街道の福生寺、長善寺、青色寺、土佐街道の梅谷寺、打越寺、円頓寺、川北街道の瑞運寺、淡路街道の長谷寺の各寺がそれで、いずれも1日行程のところにあります。ちなみにこれらの寺には、「堪忍分」として10石が与えられていました。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
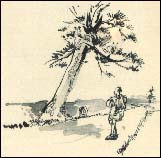 |
 |
藩政時代、街道の整備にともない、阿波五街道の両側には徳島城の鷲の門を基準として、およそ一里(約4km)ごとに松を植え、里程の目じるしとしました。これを一里松といい、幕府の一里塚と似たものでした。
今では一本も残っていませんが、川島町や池田町には、その名残を示す“一里松”の地名が残っています。 |
|
 |
|道路事業トップ|交通需要マネージメント(TDM)|
|道路づくりの推進|道路改築|道路管理|道の駅|阿波国の礎| |
|