■アキニレ群落
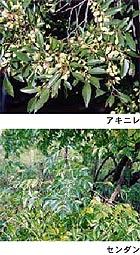 |
 ■識別ポイント 安定した低水敷に発達する夏緑樹(落葉広葉樹)が優占する高木林であり、アキニレが優占することにより識別できる。同じ夏緑高木林のエノキ−ムクノキ群落よりも群落高は低く、4 〜13m 程度である。 ■構成種 構成種は15 〜40 種程度と立地環境により大きな差がある。平均は25 種程度である。高木層ではセンダンが混生するほか、ノイバラ、アケビ、ヤブガラシなどのノイバラクラスの種の出現頻度が高い。 ■成育立地の環境特性 ほとんど安定した肥沃な立地に成立する。本群落は、数〜数十年に一度の洪水のような大規模な攪乱を受けることにより維持されていると考えられる。冠水などの攪乱頻度が低下するとエノキ−ムクノキ群落へ移行すると思われるが、詳細は検討が必要である。 ■生態的機能 発達した樹冠は鳥類の塒になるほか、営巣にも利用される。階層構造をもつため、林内の環境も多様になり、多くの生き物が利用していると思われる。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落、オギ群落、ノイバラ群落、クズ群落など、陸域側ではマダケ群落などの各種竹林、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。 ■四国での分布 吉野川、重信川、物部川において確認されている。とくに、物部川の下流には相当な面積にわたって分布している。 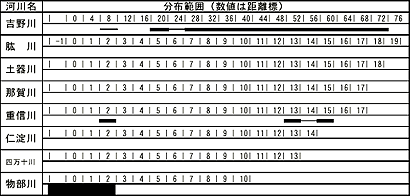 ■保全上の留意点 河川内に残された本群落は、樹林環境として貴重な存在であり、治水上問題のない範囲で、できる限り保全することが望まれる。 ■植物社会学上の位置づけ アキニレやセンダンが優占する森林については、植物社会学的には位置づけられていない。 |
|
|