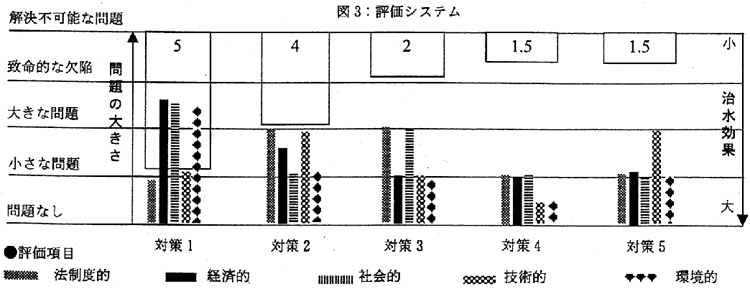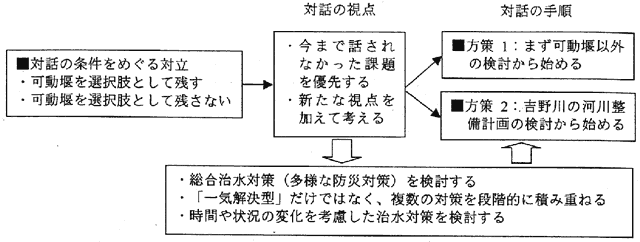
| 議事1:前回(第11回懇談会)の再整理 |
2001.2.24 第12回 吉野川懇談会 |
1.前回「たたき台」の再整理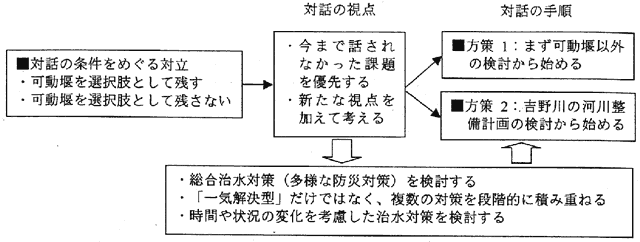
| ● | 総合治水対策など新たな視点を加えることによって、堰の改築や可動堰という枠組みを越えた多様な治水対策メニューを考えることができる。 |
| ● | 可動堰以外の検討という点では共通性がある。可動堰以外にも有効な複数案が出そろうことによって、改築の是非や可動堰を選択肢として残すかどうかということを、市民参加で話し合う基礎をつくることができる。 |
| ● | 総合治水の視点も含めて、可動堰以外の有効な複数対策案を検討することが先決。 |
| ● | 有効な複数案を段階的に実施するという選択も考えられる。 |
2.「可動堰以外」という表現について
| 前回の議論で、「可動堰」が選択肢から除外されるという誤解を招くのではないかという意見がありましたが、2/17(土)の運営委員会で、次のように整理しました。 この提案は、「検討の手順」として「まず可動堰以外」の検討から始めたらどうかということであり、そのことを提言の中できちんと説明する。 まず、総合治水対策や可動堰以外の有効な複数案がでてくることが先決であり、その複数案が従来の可動堰計画と同じレベル、あるいはそれ以上の裏付けをもった段階で、市民参加による選択が可能になる条件が整うと考えられる。 |
3.評価システム
| 2/17の運営委員会で、方策1のフローの「評価」について、「この段階で一つの案に絞るのか?」という質問がありましたので、補足します(図3)。 ここでいう「評価」は、「可動堰以外の有効な複数案」をそれぞれ、法制度上の問題、経済的、社会的、環境的、技術的、治水効果など、様々な評価軸で「評価」するということです。ですから、方策1でいう「評価」は、すべての案が評価対象になるということを意味しています。 そのような「評価」があって、「選択」の段階に入れる。それも、一つの選択ということではなく、複数選択(段階的、積み重ね型)もあるということです。 対策案の検討、評価、選択、それぞれの段階で市民参加を組み込むというのが趣旨です。 |
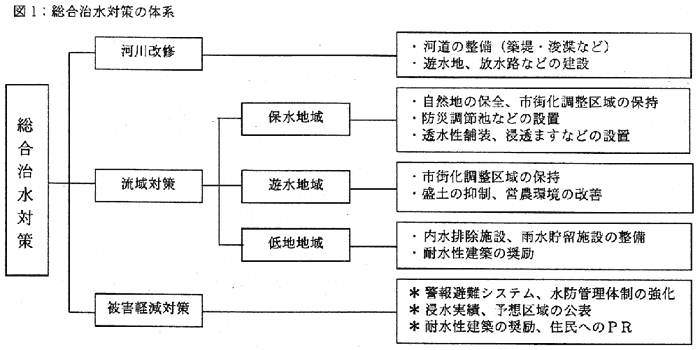
| 図2:洪水に対する安全度 洪水に対する安全度は、河川改修などによって高まりますが、一方で、河川流域の保水地(山林や水田、ため池など)が減少したりすると、川への雨水の流出が増大し、相対的に安全度が低下します。 また、これまであまり人が住んでいなかった湿地や水田が開発されて、人が住むようになると、洪水に対するリスク(危険度)が高まり、氾濫した場合には被害が以前より拡大することになります。 総合治水とは、土地利用など、様々な要因を考慮した対策を講ずるというものです。 |
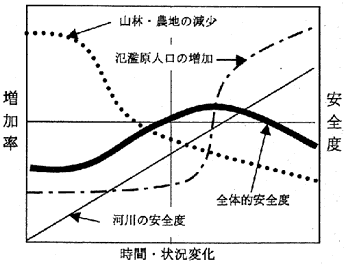 |