| ■新たな「検討の場」や「受け皿」を必要としている | |
| ・ | 事業者と団体との直接的な交渉では前に進まない(これまでの繰り返し)。意見対立やもめ事を解消するための仲介的な役割を果たすことのできる人物や機関が必要と考えられる。 |
|
・ |
アセスの会や佐野塚、みんなの会といった市民団体からの提案がすでに出されていたり、検討されようとしているが、現在は徳島工事事務所にしか「受け皿」といえるものがない。このような提案を受け止めて、総合的な議論(市民参加)ができる「受け皿」が必要と考えられる。 |
|
・ |
緩やかなテーブル、団体サポート、公開討論会、アンケート、流域ワークショップ、川へのアクションなど、この懇談会ででたたくさんのアイディアも、多くの人に認められる「呼びかけの主体」や「運営の主体」が必要と考えられる。 |
| ■「共通のテーブル」を核とした「中間提言」の再検討 | |
| ・ | 意見対立を解消して、お互いに協同して問題解決に当たるプロセスが重要である。そのためには、何らかの形で「共通のテーブル」を実現することが必要だと考えられます。 |
|
・ |
一方、「共通のテーブル」に関連して、団体訪問や懇談会では、次のような指摘がされています。 *仮に双方がテーブルについても平行線の議論になるだけでは?。 団体意見の主張の場となる可能性がある(合意を目的とした議論になりにくい)。 *「共通のテーブル」が真に市民意見を反映しうるものといえるかどうか。 市民の声なき声を反映することが重要。 *自分たちの案を持っている以上、テーブルにはつかないのではないか?。 |
|
・ |
「共通のテーブル」を合意形成の核に位置づけると、そこでは何らかの歩み寄りが必要になる場面がでてきたり、そこでの合意に従うことが必要になる。しかし、団体としての考え方をもっているので、なかなか意見を変えるということは難しいかもしれない。また、団体の独立性を確保するという視点で考えると、「中立的な検討の場」をつくり、そこに様々な意見が反映できるという仕組みを提案した方がよいと考えられる。 |
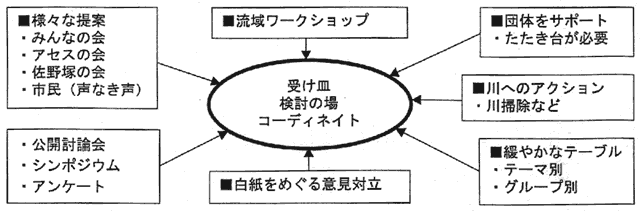
| ■第三者による中立の「市民参加検討委員会」(仮称)を設ける | |
| (1)第三者で構成する | |
| ・ | 市民団体代表で構成する「共通のテーブル」が実現しなかったのは、その条件をめぐる意見対立があり、それらを調整する第三者的な機関がなかったことがひとつの要素として考えられる(団体訪問での意見:誰がレフリーとなるのか?など)。 |
|
・ |
「参加条件」には、第十堰をどうするかという団体の意見が反映されるため、「検討の場」が成立しにくい。また、団体の立場から見ると、事業実施の手続きとして単に利用されるだけではないかという不信感がある(どのように意見が反映されるのか保証がないという団体訪問での意見)。団体の意見を市民に広げ、多くの支持を得るというのが市民運動の原点。こうしたことを配慮する必要がある。 |
|
・ |
大事なことは、意見の異なる団体も含めて多くの市民の意見を受け止められる「場」なり、「機関」が用意されていることである(参加の仕組み)。 |
| ・ | 最初の「受け皿」を用意して、その「受け皿」を通じて、各団体との意見交換や公開討論会(緩やかなテーブル)などを積み重ねることが当面必要と考えられる。 |
| ・ | 多様な意見の「受け皿」として機能するためには、団体等の当事者ではなく、中立的な第三者による運営が望ましいと考えられる。 |
| (2)主な役割は何か | |
| ・ | これまでの経過や問題点を整理し、検討すべき課題を提示する。 |
| ・ | 団体や市民の意見を集約し、課題を整理する。 |
| ・ | 計画プロセス、市民参加プロセス、意思決定プロセスに関する基本的な課題を提示する。 |
| ・ | 問題解決に向けた基本方向や仕組みについて提示する。 |
| ・ | 「次の検討の場」を提示する。 |
| (3)従来の審議委員会との違い | |
| ・ | 従来の審議委員会は、事業者の計画の妥当性を判断するというものが多かった。意見が分かれている問題について是非を判断するというのは適切とはいえない。多様な意見を受け止め整理するということを中心的な役割とする。 |
| ・ | 事業者側が用意した資料を基に議論するのではなく、それぞれの委員が創造的な提案を行うものとする。 |
| ・ | 団体や市民との話し合いにおいては、進行役的な役割を果たす。 |
| ・ | 自由な議論(提案)を保証する。 |
| (4)構成 | |
| ・ | 異なる意見に耳を傾けることができる人材、中立的な立場で議論できる人材、バランス感覚を備えている人材、もめ事や新しい課題に対して創造的な提案ができる人材、そして、第十堰問題をいい形で解決したいという意欲のある人材。 |
| ・ | 一般市民、学識経験者、NGO(非政府組織)、NPO(非営利団体)などで構成する。 |
| ・ | 円滑な議論ができる適切な人数とする。 |
| ・ | 課題が多岐に渡るため、必要に応じて複数の専門部会等を設置することも考えられる。 |
| ・ | 議題の検討や討論内容の整理、資料作成などを行う運営委員会を設ける。 |
| (5)委員の選定方法 | |
| ・ | 全国的NGO /NPO団体、あるいは弁護士会、国際影響評価学会などからの推薦を受ける。 |
| ・ | 第十堰に関わる市民団体などから推薦を受ける。 |
| ・ | 一般市民は、基本的に公募によるものとする。 |
| ・ | 事前に、選定方法や人材、NGO/NPO組織等について、団体や市民からの意見を募り、それを反映した選定方法を検討する。 |
| ・ | 委員会の役割や選定基準等を定めることとし、市民からの意見を募る。 |
| ・ | 誰が選定するかということについては、上記の各団体・組織等の代表と事業者等で構成する選定委員会を設けることを検討する。 |
| (6)委員会の運営方法 | |
| ・ | 事業者(国土交通省)は、委員会の自由な議論や提案をすることを保証し、尊重する。 |
| ・ | 委員会をサポートする運営委員会については、委員の中からの運営委員が中心になり構成する。 |
| ・ | 運営に当たっては、第十堰に関わる団体や市民からの意見を受け付け、委員会の運営に反映させる。 |
| ・ | 委員会の議論は、委員の提案を軸に行うものとする。 |
| ・ | 委員会には、事業者側の責任者が必ず出席し、議論のプロセスの各段階で、意見や提案が意思決定に反映されるようにする(討議のプロセスでの意思決定の積み重ね)。 |
| ・ | 委員会は公開で行う。 |
| ・ | 委員会での議論は、独自の広報手段(かわら版など)を通じて、広く市民に知らせる。一方的な広報ではなく、双方向のコミュニケーションが図れるよう工夫する。 |
| ・ | 広く市民的な討論が行われるよう、公開討論会等を適宜開催する。 |
| (7)その他 | |
| ・ | ここで提案している「市民参加検討委員会」は、市民的な検討の場を通じて合意されたものではないので、一定の限界があり、したがって、行政主導の「御用委員会」という批判がでるかもしれません。 |
| ・ | しかし、制度的な枠組みが確立していない段階では、行政の責任で最初の「検討の場」を設けるというのは、ある程度やむを得ない。従来の審議委員会の問題点をできるだけ改善し、できるだけ多くの市民意見を反映する運営の実体をつくるということが重要だと思います。 |
| ・ | 市民参加と合意形成、第十堰問題の解決を取り扱う委員会としての実質的な機能(中立的議論、創造的議論、市民意見を反映した議論、双方向のやりとり、具体的な提言など)によって評価されると考えます。ベストではないが、よりベターな「検討の場」から再スタートしたらどうかという提案です。 |
| ・ | 第十堰に関わる団体を軽視するということではなく、この「市民参加検討委員会」を立ち上げる前に、事業者と市民団体とのコミュニケーションを図ることが重要です。 |