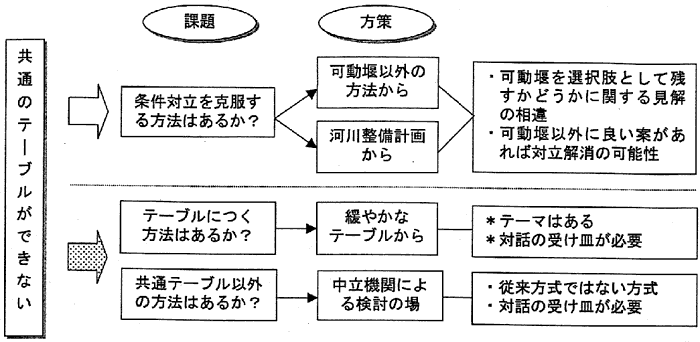
| 議事1:対話の実現に向けた方策を考える(その1) |
2001.2.3 第11回 吉野川懇談会 |
1.対話の実現に向けた課題の整理
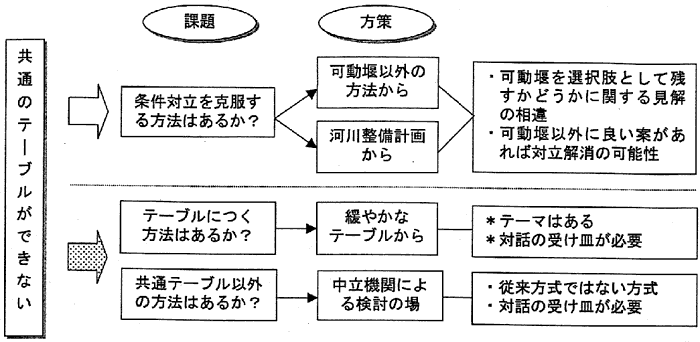
2.対話の実現に向けた方策(案)
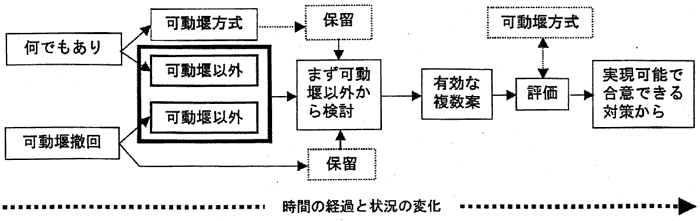
*両者は完全に対立しているように見えますが、上図のように分析してみると、「可動堰以外」というところは「共通」しています。
まず、共通項を優先し、その間の可動堰の扱いを整理することが考えられます。
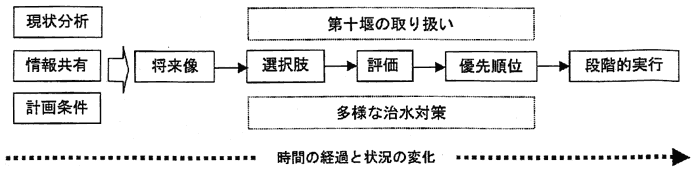
| ・ | これまでの議論は、可動堰計画の枠組みの中で行われていますが、その外にはたくさんの課題が存在しています。可動堰以外の多様な治水対策もそうですし、そもそも吉野川の将来像というものが話し合われていない。 |
|
| ・ | ですから、「可動堰あり・なし」を保留し、可動堰以外の方法から話し合う、あるいは第十堰を一旦棚上げして、吉野川全体の将来像(河川法の河川整備計画の論議)から話し合うことが考えられます。 |
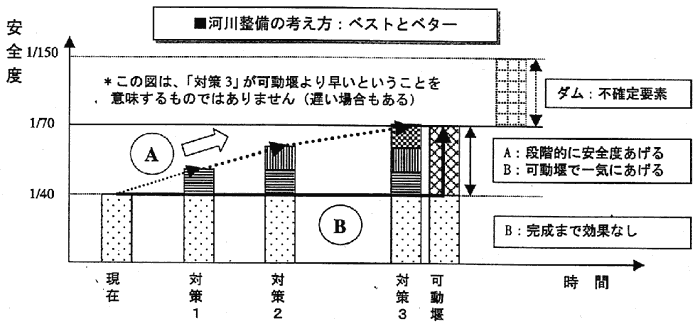
| ・ | 治水対策には多様な方策があり、また、計画目標をひとつの方法で一気に達成させようとする考え方(ベスト)と、複数の有効な対策を積み重ねる考え方(ベター)があります。前者は、完成するまで効果を発揮できません。後者は、少しずつ安全度があがります。 |
| ・ | つまり、整備計画では、どれがいいかということだけでなく、どのようにして安全度を上げていくかという考え方が重要なテーマになるということです。したがって、可動堰計画以外に実現可能な対策があるのか、複数の案がまず検討される必要があるし、それらをどのように組み合わせていくことができるかを検討する必要があるでしょう。 |
| ・ | もうひとつ大事なことは、時間の経過や状況の変化を考慮に入れることです。可動堰計画は当時の選択ですが、それも一応「白紙」から議論しましょうと、変化しています。話し合いが実現して、仮にある計画が合意されたとしても、それはあくまでもそのときの選択でしかありません。上の図で、「対策1」を実施して「対策2」に移ろうとしたときに状況が変化していることもありうる。その時点でまた検討されるべきものです。そのときに新たな「対策4」がでてくるかもしれないし、目標そのものを見直すこともありうる。 |
| ・ | 「白紙」をめぐって「可動堰あり・なし」という論争は、対話の入り口論議として重要であり、それぞれ根拠のあることですが、話し合いの発展過程を大事にするという視点に立つこともできるのではないでしょうか?。 |