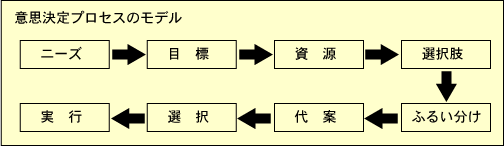
議事1:団体ヒアリングの中間まとめ(3)
7.ヒアリングのまとめ
(1)共通理解だと思われる部分と見解の相違(白紙勧告)
| ●共通理解 |
| 計画のない段階、つまり、吉野川の現状や課題、問題解決の方向性を共有化するところに立ち戻って議論するという点では、微妙な食い違いを含んではいますが、それでも共通性があると思われます。 これは、白紙、つまり計画案というものがなくなったわけですから当然といえば当然ですが、市民参加のスタートラインを計画の前の段階におくという共通理解があるとしたら、重要な意味を持つと考えられます。 建設省の可動堰案があってそれも含めた他の案を話し合うというのと、基本問題に立ち返るというのでは、根本的な違いがあるからです。 ただ、可動堰案は現実に存在していたわけですから、完全にクリーンな状態で話し合うことができるかどうかは、難しい課題があると思われます。 |
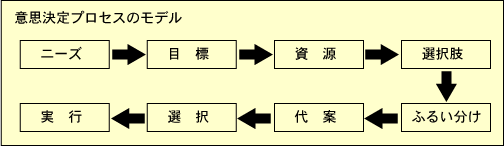 |
| ●見解の相違 |
| 白紙に戻って話し合うにしても、可動堰が選択肢に含まれるかどうかで、大きく見解が異なっています。したがって、この問題で何らかの整理がつかないと、話し合いの場の実現は極めて困難な状況にあると思われます。 話し合いというのは、心理的な面や手続き的な面が大きく影響します。お互いが協調的な解決を望むというような状況がつくられることが必要ですし、話し合いの障害になっている問題に対する何らかの良いアイディアがでてくるかどうかが大きな課題としてあると思われます。 |
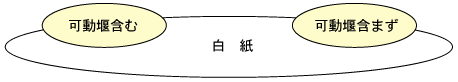 |
(2)建設的な提案
| 団体ヒアリングを通じて大変貴重な意見の数々をいただいたと思います。たくさんの貴重な意見の中から、ここでは二つを取り上げてみます。 |
| ●共通のテーブルへの土壌づくり |
| 私たちは、「共通のテーブルをつくろう」ということを提案し、そのために努力しようとしています。そのことは間違っていないと思いますが、しかし、その前に「どうやってその土壌をつくるのかが大事だ」という指摘を、いくつかの団体の方から受けました。 先に述べたように、共通のテーブル実現へのハードルはまだ高いように思われます。そのことをふまえて、新たな観点から「土壌づくり」の提案を検討する必要があると思われます。 |
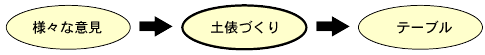 |
| ●吉野川全体への共通理解を深める |
| 吉野川流域全体の課題に対する知識や理解を深めることが大事だという意見をたくさんいただいています。これは、可動堰に反対とか賛成とか関係なく、共通しています。 これは、「共通のテーブルの土壌づくり」という点でも、仮に「共通のテーブル」ができたとしてその後の話し合いにとっても基本になる事柄です。 しかし、どうやって共通理解を深めるのかとなると具体化されたものは今のところありません。 私たちは、まず第十堰の課題からということで「中間提言」をまとめましたが、もうひとつの課題、吉野川全体の参加の仕組みをどうするかといった課題が残されています。この課題にも取り組み、最終提言に向けた検討を開始する必要があると思われます。 |
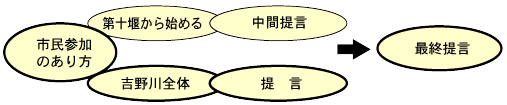 |