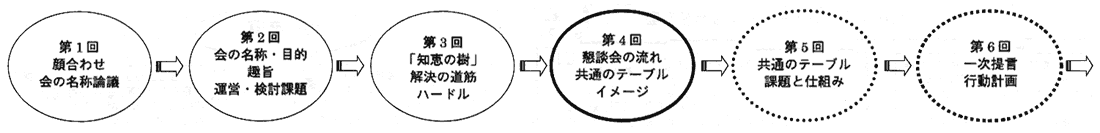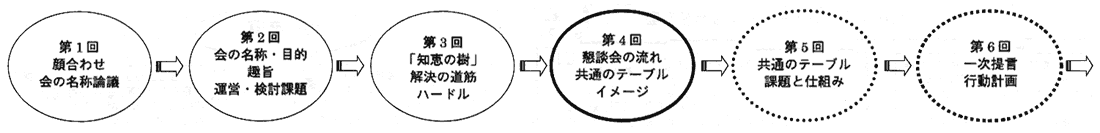| ■第2回懇談会 |
| ●会の名称 |
|
・「明日の吉野川と市民参加のあり方を考える懇談会」とし、副題に「第十堰から始める新しい川づくり」を入れました。 |
| ●会の趣旨 |
|
・吉野川における新しい市民参加の仕組みを考える。
・第十堰について、「みんなでいい解決」を目標に、共通のテーブルを用意し、多くの住民が納得できるものを市民参加によってつくりだしていく。
・吉野川への恩返しの行動をつくりだす。 |
| ●会の目的 |
|
・第十堰を含む吉野川における参加と対話の方法を検討し提案する。
・「対話の場」の実現に向けて働きかけをする。 |
| ●検討課題 |
|
・吉野川と第十堰の問題と魅力を抽出し共有する。
・参加のあり方(参加の場の設定方法、対話のルール、住民意見の把握と反映方法、市民・行政・専門家の役割と関係、河川法に基づく新しい仕組み等)を検討する。
・行動計画(学習、川での活動、流域住民との意見交換会等)を検討する。 |
|
|
| ■ 第3回懇談会 |
| ● 知恵の樹 |
|
・これまでの討論やアンケートの中で出てきたメンバーの意見を整理し、問題解決の道筋を「知恵の樹」としてまとめました。 |
| ●グループ討議で出た意見 |
|
「第1グループ」
・この会は中立的な立場で話し合いのテーブルにつくための仲人役をし、団体に働きかけを行う。
・技術や環境のことは協力してやるのがベスト
・合意できるところからスタート
「第2グループ」
・対立点を拾い出して分析していく
・第三者機関が加わった話し合いの場をつくる
「第3グループ」
・川を大切に、きれいにという共通の理念に基づくアクションを起こし、土俵をつくる
「第4グループ」
・歴史も含めた治水、利水を考える
・流域交流を形成することで合意形成が進む
・この懇談会は行司役。いろんな考えの人が対等にあがってこられる土俵づくり。
・みんなが納得できる情報、データーの精度
・計画条件の共有が大事
「第5グループ」
・建設省が白紙撤回すれば対話はすぐ実現する。
・外国も含めコンペ(設計競技)をする
・現場を見たり調査することは共有できるはず
・賛成、反対に分かれ徹底討議し、解決つかないものは専門家に任せる? |
|
|
| ■これまでの到達点 |
| ●懇談会メンバーの共通認識 |
|
・賛成、反対ではなく、中立の立場で、共通のテーブル実現に向けて行動していくということが、ほぼ全体の共通認識になってきたと思われます。 |
| ●共通のテーブルのプレステージ |
|
・懇談会には、第十堰に関して賛成、反対、中立、様々な考えをもった方が参加しています。この懇談会自体、「共通のテーブル」のひとつになっているわけです。私たちは、共通のテーブル実現という目標に希望と確信を持っていいのではないでしょうか。
・このような場のあり方が、次のステップに向けたひとつの道筋を示していると思います。
・「いい解決」「いい市民参加」は「いい人間関係」をつくることであり、「いい人間関係」から「いい解決方法」が見つかるのだと思います。 |
| ●問題解決の道筋のイメージ:知恵の樹 |
|
・これまでの意見を「知恵の樹」としてまとめたことにより、解決へのイメージが見えてきました。 |
| ■今後の課題 |
| ●「知恵の樹」の具体化 |
| ●ハードルの克服 |
| ●共通のテーブル:イメージの具体化 |
|
*いろんな団体に出かけていこうということが確認されていますが、何を話すのか、何を提案するかがまだ不十分だと思われます。
*共通のテーブルのイメージをもっと具体化しましょう。 |
|
|
■吉野川全体、第十堰、
なにから始めるか? |
| ●第3回懇談会で出た意見 |
|
・ 吉野川全体、第十堰、どちらから始めるのか最初に決めないと討論のしようがない。
・ 今の集まりは下流の人が多く、力量の問題もあるので吉野川全体からというのは難しい。
・ 全体をやるなら、流域全体に呼びかけ、流域全体の構成ですべきではないか。
・ 吉野川全体とか清掃といっても、第十堰への関心や活動している人たちの動きとかみ合わない。 |
| ●第1回懇談会、第1回アンケートから |
|
・ 流域の問題から議論を始め第十堰のあるべき姿を浮かび上がらせていく
・ 第十堰解決のための方法を探りたい |
| ●会の名称(副題) |
|
・ 「第十堰から始める新しい川づくり」 |
| ●第3回懇談会グループ討議 |
|
・ 中立の立場で関係団体に出かけていく
・ 対立点を拾い出し分析する
・ 川を大切にという共通理念に基づくアクションを起こし土俵をつくる
・ 上下流交流、流域交流ネットワークをつくる
・ 吉野川全体を見ながらも、緊急性の高い第十堰に絞ることになるのではないか
・ 賛否両派に分かれて第十堰のことを考える方がいい |
| ■どちらから始めますか? |
|
|