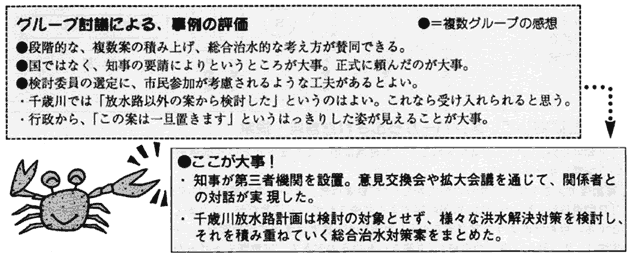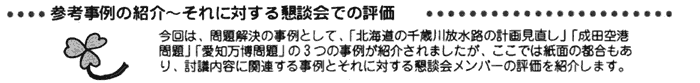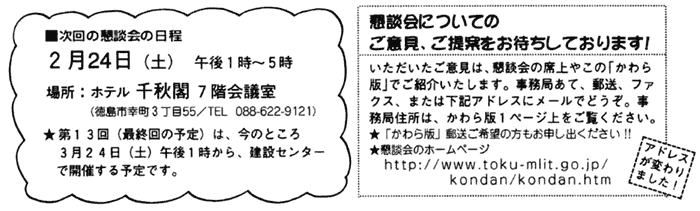|
●委員会設置に至る経緯
昭和50年・56年の洪水を契機に、国は昭和57年に「千歳川放水路計画」を策定したが、環境保護団体や漁業関係者らの反発が強まる。一方、放水路推進の組織も発足し、次第に賛否両論の対立が鮮明になり混迷の度合いが深まる。平成9年2月に、堀知事が「一度立ち止まって適切に対応されるべき」との見解を示し、国も「一度白紙に戻って、前提条件なしに対話の場を設けたい」と表明。しかし、道指導漁連、自然保護8団体は、「計画の白紙撤回が条件」として対話の場は実現しなかった。その後、知事の要請により、平成9年9月に7名の学識経験者を委員とする「千歳川流域治水対策検討委員会」が正式に発足した。
委員会は、約1年半に亘り、23回実施。この間、反対団体や関連首長を交えた「拡大会議」を16回、反対団体を含む関係者との意見交換会を5回実施している。委員会は、平成11年6月に5項目(10の対策案)を知事に提言。道の意見をつけて国に提出され、国は千歳川放水路事業の中止を決定し、北海道開発局と北海道の共同による「千歳川流域治水対策全体計画検討委員会」が新たに設置された。
●検討委員会の提言(要旨)
・基本的に、千歳川および石狩川の合流点を含めた流域における総合治水対策を推進する。千歳川放水路計画については検討の対象としない。
・検討委員会は、千歳川と石狩川との合流点整備をはじめ、有効であると思われる様々な洪水解決対策を検討し、総合治水対策室としてまとめた。これらを実施することによって千歳川流域の治水は著しく改善されると判断する。新遠浅川案のような流域外対策案は、総合治水対策の進行状況をみた上で、万一それらが著しい効果を果たさないと判断された段階で、新たな検討事項として取り上げるべきものと考える。
|