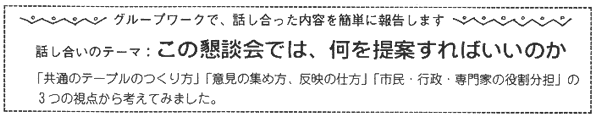
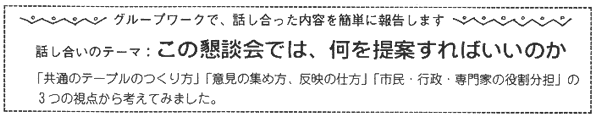
| 懇談会の後半は、6グループに分かれ、3つの議題について意見を出しあいました。 初めに個々人でふせん紙に自分の意見を書き、それをグループの中で出しあいながら、大きな紙に貼って意見をまとめていきました。 30分という短時間だったので、まとめきれない部分もありましたが、だいたい次のような話し合いがされました。 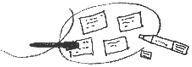 |
 |
 |
|
●グループ2 ・住民の合意により事業の方向が決まれば、担当の行政機関に専門性を持って検討してもらう。 ・行政側だけで流域住民に説明してもその効果は疑問。地域代表が勉強して、この代表により地域の各団体に向けて説明討議する方法も良い。 ●グループ3 ●グループ5 ●グループ6 |