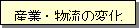 -観光関連産業を中心とした波及効果- -観光関連産業を中心とした波及効果-
観光入込客数の増加に伴い、西瀬戸自動車道沿線では、観光関連産業やホテル・旅館業、運輸業の売上が増加している。その他にも、地元の飲食店・小売店の売上増加や、新規出店・新規雇用創出といった効果が現れている。
98年に瀬戸田町を訪れた観光客数は134万人だったが、99年は200万人を見込んでおり、一人当たりの観光消費額が昨年と同じ場合、約23億円の収入増加となる。
愛媛県越智郡や広島県の沿線島嶼部で、コンビニエンスストアの出店計画が活発化している。
今治公共職業安定所によると、観光関連の飲食業やサービス業の求人が増加傾向にあり、6月の一般求人は卸売・小売・飲食店関連が160人(前年同期比19%増)、ホテルなどサービス業が249人(同33%増)となっている。
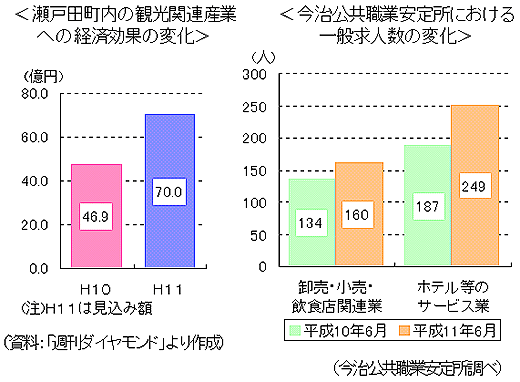
|