鳥 類
|
 |
ヤマセミ
水の豊かな渓流などに生息。一直線に飛び、キャラ、キャラの鳴き声が特徴。
|
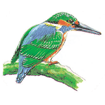 |
カワセミ
水面を低く速く直線的に飛び、水中で餌を捕獲。ツィーと鋭く鳴きます。
|
 |
オシドリ
10〜4月頃に湖などに渡来。オスはオレンジの生殖羽をもち、メスは濃い灰色です。
|
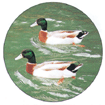 |
マガモ
9〜4月頃、湖沼に渡来する冬鳥。オスは白い首輪、メスは黒斑点が特徴です。
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る |
ほ乳類
|
 |
ムササビ
足の間の皮膜を広げて滑空します。夜行性で民家や神社の屋根裏にも生息。
|
 |
ニホンリス
主に松林に生息。小枝などで樹上に巣を作ります。キノコや種子、昆虫が主食。
|
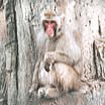 |
ニホンザル
十数頭〜百数十頭の群れで暮らし、遊動生活を好みます。
|
|
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
植 物
|
 |
イワギリソウ
5〜7月、紫色の美しい花をつけます。仁淀川沿いにも自生することがあります。
|
 |
イヌトウキ
根が薬用になるトウキに似ているが、役に立たないことから「犬」とつけられました。
|
 |
ユキモチソウ
暗い場所に生え、4〜5月に開花します。花の形から「雪餅草」と呼ばれる珍しい種。
|
 |
ヒメウラジロ
小さくて葉の裏が白いことから「姫裏白」といわれます。岩地に生育。
|
 |
オオバノハチジョウシダ
和名は「大葉の八丈羊歯」。長さ0.4m〜1mのやや大型のシダで谷沿いに生育。
|
|
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
魚介類
|
 |
タカハヤ
ダム湖に注ぐ支流に生息するコイ科の小魚。水生昆虫などを食べます。
|
 |
カワヨシノボリ
中・上流域に生息。 大渡ダム周辺では、 岩屋川など流れのある川でみられます。
|
 |
アマゴ
「清流の女王」といわれる渓流魚。釣りの難しさと味の素晴らしさで人気です。
|
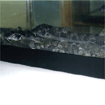 |
カマツカ
食べ物と同時に飲み込んだ砂をエラから出して前進。砂から眼だけ出して潜っていること
が多い。
|
 |
カワムツ
深く掘れたところや淵の植物が垂れさがる、流れのゆるい場所などに棲みます。ときどき争うことも。
|
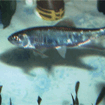 |
オイカワ
川底に石のある場所が主な住みか。オスは初夏の産卵期、鮮やかな婚姻色を帯びる。
|
 |
イシドジョウ
水のきれいな川の上流域に生息。石についた藻類や水生昆虫が主なエサ。
|
 |
テナガエビ
川の中流や池など、流れが緩やかな砂泥域に生息。夜になるとエサを求めて活動する。
|
 |
サワガニ
水のきれいな小川・谷川にすむ、日本でただ一種の純淡水性のカニです。
|
|
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
は虫類
|
 |
ニホンマムシ
やや太短く、ずんぐり型のヘビ。強い毒をもち、日本本土で最も危険とされる。
|
|
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
両生類
|
 |
カジカガエル
4〜7月頃、フィ、 フィ、フィ、フィーと美しい声で鳴きます。餌は昆虫など。
|
 |
タゴガエル
4〜5月頃、岩のす きまや水中に産卵します。昆虫やクモが餌となります。
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
昆虫類
|
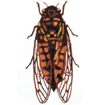 |
ハルゼミ
4〜6月頃、晴れた日の松林でムゼー、ムゼーと合唱して鳴きます。
|
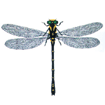 |
ムカシトンボ
別名「生きた化石」。日本とヒマラヤだけに生息します。3〜5月頃にみられます。
|
 ページのトップに戻る ページのトップに戻る
|
 見どころ一覧に戻る 見どころ一覧に戻る |