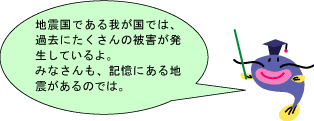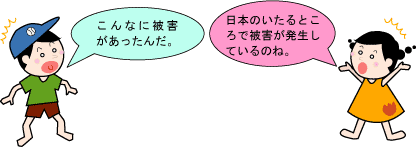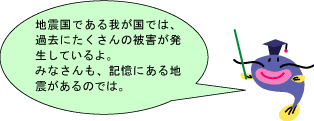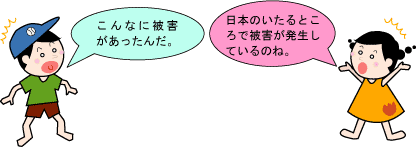| ▲このページのトップへ |
| ○明治三陸地震(1896年)・昭和三陸地震(1933年) |
|
明治三陸地震と昭和三陸地震は、ともに岩手県三陸沖の日本海溝付近で発生しました。
明治三陸地震は、地震動(揺れ)はあまり大きくなく、最大でも震度4程度であったにもかかわらず、津波高さは最大で38.2m(岩手県三陸町綾里)にも達し、津波による犠牲者が我が国最大の約22,000人にも及びました。なお、この津波高さ38.2mは、明治以降に日本付近で記録された中では最大と言われています。
一方、昭和三陸地震は、明治三陸地震より地震動(揺れ)が強く、太平洋の沿岸地域を中心に震度5が観測され、津波高さは明治三陸地震と同じ地点で23.0mに達しました。
|
| (出典:「地震調査研究推進本部」) |
| |
 |
明治三陸地震の震度分布図
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
| |
 |
明治三陸地震による各地の津波高さ
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
 |
昭和三陸地震の震度分布図
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
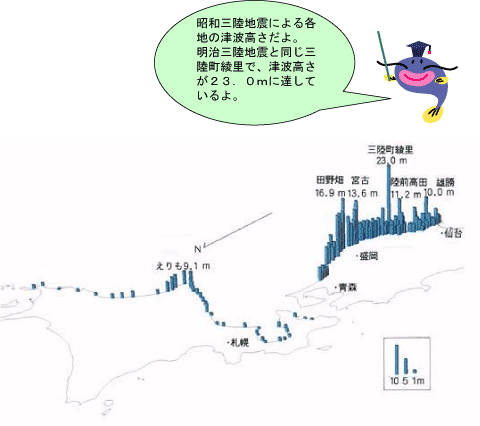 |
昭和三陸地震による各地の津波高さ
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
| ▲このページのトップへ |
|
|
チリ地震は、南米のチリ沖で発生した地震で、地震の規模はモーメントマグニチュードMw9.5で、世界でも最大級の地震です。
この地震による津波はチリの海岸だけにとどまらず、広く太平洋全域に伝播し、遠く日本でも大きな被害が生じました。日本へ津波が押し寄せたのは地震から約22時間後で、太平洋岸のほとんど全域で津波が観測されました。津波の高さは1〜4mでしたが、太平洋沿岸の各地で大きな被害が発生し、全国で死者・行方不明者が142名となりました。
|
| (出典:「地震調査研究推進本部」) |
| → |
チリ地震津波の詳しい内容はこちらから |
| → |
被害状況写真はこちらから
■須崎港
(出典:「四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所」)
|
|
 |
 |
 |
チリ地震津波における日本外洋沿岸の津波高さ分布
(出典:渡辺偉夫著「日本被害津波総覧[第2版]」)
|
| ▲このページのトップへ |
| ○日本海中部地震(1983年) |
|
日本海中部地震は、男鹿半島沖から津軽海峡の西側にかけての広い範囲を震源域として発生した地震であり、秋田市、むつ市、深浦町などで震度5が観測されました。
この地震により大きな津波が発生し、津波の高さは秋田県八竜町で6.6mに達しました。また、震源域が陸域に近かったため、津波は速いところで地震発生からわずか7分後に押し寄せ、逃げ遅れた多くの人が犠牲となり、全体の死者104人のうち100名が津波によるものでした。
|
| (出典:「地震調査研究推進本部」) |
 |
 |
日本海中部地震の震度分布図
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
 |
日本海中部地震による各地の津波高さ
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
| ▲このページのトップへ |
| ○北海道南西沖地震(1993年) |
|
北海道南西沖地震は、渡島半島中央部の西側の範囲を震源域として発生した地震であり、北海道寿都町、江差町、小樽市、青森県深浦町などで震度5が観測されました。
津波高さは、奥尻島で約30m、渡島半島の西岸でも最大7〜8mに達し、震源域が奥尻島や渡島半島に近かったため、地震発生後
4〜5分で津波が押し寄せ、多くの人が犠牲となりました。特に、奥尻島の青苗地区では、津波と地震後に発生した火災によって集落が壊滅的な被害を受けました。
(出典:「地震調査研究推進本部」)
この地域では、日本海中部地震(1983年)でも津波被害を受けており、地元の防災意識は高く、地震発生直後に避難をした住民も多かったのですが、津波が到達する時間が速かったため逃げ遅れるなどして多くの犠牲者が出ています。
|
 |
|
|
 |
 |
北海道南西沖地震の震度分布図
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
 |
北海道南西沖地震による各地の津波高さ
(出典:「地震調査研究推進本部」)
|
| ▲このページのトップへ |
| ▲目次へ |